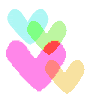
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 3
( 前頁 / TOP / 次頁 )
『 こっちくんなよ、ブス! 』
文字をつづる手が止まった。
ぶるん、と強く首を振り、きゅっ、と口を引き結ぶ。
拳の形に両手をかため、ぶるんぶるん、と首を振った。
「だめよ。踏み出さなければ始まらないんだから!」
うむ、と気合いを入れなおし、オフィーリアは机に突っ伏す。
しこしこ文字をしたためて、書きあげた便箋を眺めやり、頬杖で、とんとん机を叩いた。相手への呼びかけで始まる短い手紙は、こんな言葉で終わっている。
──あなたをお慕いしています。
嘆息し、くしゃくしゃに丸めて脇にどけた。
紙くずがいくつも転がるかたわら、まっさらな便箋を改めて据える。窓辺の机にかがみこみ、再びペンを走らせた。
窓辺の青葉が、ちらちらとまぶしい。
蝉がみんみん鳴いている。主不在につき、午後の仕事はしばらく休み。皆、街に繰り出しているのか、昼下がりの寮内は、ひっそりとして音もない。
やがて、ふう、と息を吐き、書き直した手紙を眺めやった。
文面を検分し、オフィーリアは、うむ、とうなずく。ふうふう吹いてインクを乾かし、ていねいに折り畳んで、薄桃色の封筒にいれた。
手をつき、椅子から立ちあがりかけて、ちら、と右手に目を向ける。
「……お母様、お怒りになるかしら」
ひしゃげてしまった眼鏡のツルを、溜息まじりに指先でなでた。机の端に置いてあるのは、彼が踏んで割ってしまった眼鏡だった。領邸に入るお祝いにと、母が買い与えてくれたものだ。
ぶるん、と首を振り払い、椅子を引いて席を立つ。
きゅっ、と口を引き結んだ。
「いざ出陣っ!」
決意も新たに拳を握り、扉に向けて踏み出した。
舗道の石畳の照り返しが厳しい。
街路を歩くと、汗が額をしたたり落ちた。熱風が吹きつけ、眼鏡が曇る。それでも、いてもたってもいられなかった。
じっとしては、いられなかった。
今は真夏の昼時だ。外が暑いのはわかっている。だが、寮の涼しい部屋にこもって、本を読んでいる気にはなれなかった。
寮の部屋にこもっていては、彼には確実に会えないけれど、こうして街を歩いていれば、必ず会わないとは言い切れない。現に、昼前に出てきた時には、彼に会うことができたではないか。眼鏡がなくて難儀しながら歩いていたら、つまずいて転びそうになった体を、彼が支えて助けてくれた。姫の危機を救う王子様であるかのように。
奇跡は起きる。そう、奇蹟だと思った。こんなことが起きるのは奇蹟だと。偶然などではありえない。きっと運命の成せる業──。
もっとも、彼は急いでいたようで、通りかかった友人に預けて、どこかへ立ち去ってしまったが。
『……なんでザイなんすかね 』
ふっと、あの声が脳裏をよぎった。
眼鏡の工房に付き添ってくれた、黄色い丸眼鏡の禿頭の彼は「よりにもよって」と先を続けた。遠回しに、やめておけ、と言われた気がした。いや、横をぶらぶら歩きつつ、彼ははっきりそう言った。
『 あんたにゃ悪いが、脈がない 』
足が、知らぬ間に止まっていた。
きゅっ、と口を引き結ぶ。
「ううん! 弱気はだめよオフィーリア! 何事も成せばなる! そういうものよ!」
己を叱咤し、ぷるん、と強く首を振った。拳にした両手を振って、昼の街中をずんずん歩く。歩く。歩く。ずんずん歩く。
白い襟に、紺の服。ラトキエ領邸のメイド服。こんな制服を着ていると、男たちは品定めを始めるのが常だった。若い娘が居並ぶ中でも、特別な一人を選ぶために。そして、まず真っ先に、自分が「対象外」として脱落したのが、オフィーリアにはその都度わかった。
異性の目は残酷だ。あたかもそこにいないかのように、彼らの視線は素通りする。理由は薄々わかっていた。子供の頃からかけている眼鏡のせいだ。
男とは非寛容な生き物だ。見てくれこそが、彼らには価値の全てなのだ。それがどれほど残酷なことか、比べられるのがどれだけ嫌か、そうした彼らの言動が、何もしていない善良な相手をどれほど傷つけるものなのか、彼らにはまるで分かっていない。分かろうともしない。そうして、無邪気を装い、言うのだ。
"だって、仕方がないじゃないか"
彼らに理屈は通用しない。努力のしようもないのことでも。今まで一人の例外もなく、そうした憂き目にあってきた。どれほど同じ事がくり返されても、この痛みには慣れることがない。
見慣れた日常の風景に、ふい、と紛れこんだあの彼は、他の誰とも違っていた。
見目麗しい同僚の中でも、彼の視線は一様だった。選り分ける素振りさえ見せなかった。かわいい顔立ちの他の娘と、彼は同列で扱ってくれた。これまでの男たちがしてきたように、のけ者にしたりしなかった。彼には、なんの頓着もない。
それだけの理由だった。それだけで十分だった。あの彼に恋した理由は。
真っ白いレースのついた、真新しい靴下をおろして、はいた。
鏡の中を覗きこみ、不慣れな白粉をはたいてみた。
唇に紅を引いてみた。ごくごく薄い桃色の。工房に付き添ってくれたあの彼が「これなんか、あんたにかわいいですよ」と選んでくれた眼鏡の赤い縁に合わせて。
本当は、まつ毛だって長いのだ。毎晩百回は梳いているから、髪だって、さらさらだ。吹き出物ができないように、甘い物だって控えている。自分でも知らない内に、足が小走りになってしまう──
のんびりと気だるい、夏の昼下がり。
まだ、通りに人けはない。──いや、前方の街角に、すっと人影が現れた。目元にかかる薄茶の髪、硬そうな肩、すっと伸びた痩せた背中──足が止まり、息を呑む。ひょい、と相手が振りむいた。
「おや。奇遇ですね。一日に二度も、お会いするとは」
あわあわ両手を組み合わせ、オフィーリアは赤面でうなずいた。「え、ええ! とっても奇遇ですわっ!」
またも街角で鉢合わせ。やはり、奇蹟は起きるのだ!
人けのない街角に、ザイは視線をめぐらせた。「ひょっとして、あれからずっと、この辺りにいたんスか? 飯でも食ってきたら、どうスかね」
「いえっ! 寮で済ませてきましたのっ!」
「そいつは残念。俺はこれから食いに行こうかと思ってたんで」
「あっ、それなら、わたしもご一緒に──」
「今、食ったって言いませんでした?」
「──えっ、──あっ、でも、あのっ!」
「ご心配なく。俺は適当に済ませますから」
辺りを見まわし、腕を組む。「ともあれ、このカンカン照りだ。いつまでも外にいるのは体に毒ってもんですよ。暑さで脳天いかれる前に、寮の方へ戻っちゃどうです?」
「──あ、あの、ザイさん」
かあっと赤面してうつむいた顔を、オフィーリアは振りあげる。「こ、こ、この眼鏡、新調──」
「よう、ジョエル!」
──え゛っ? と引きつり笑顔で固まった。
背筋をなでる嫌な予感。なにやら前にも、似たような展開があったような……?
はたして、西の街角を通り過ぎようとしていた男が、気がついたように振り向いた。
すぐさま、こちらに駆けてくる。どうやら、あれが "ジョエル" らしい──はた、とオフィーリアは大事なことを思い出した。
「あ、あの、ザイさん──こ、これをっ!」
わたわたポシェットに手を入れる。だが、何かに引っかかっているのか出てこない。昼食後にしたためた、この彼あての薄紅の手紙が。
ぐんぐん近づくジョエルの姿と、かたわらのザイとを見比べて、あたふた、おろおろ、うろたえる。
そうこうする内、ジョエルが速やかに到着した。
ふわり、と何かが、足を止めた髪から香った。わずかにオフィーリアは眉をしかめる。本能が告げる微かな危険。そう、これは
火薬の匂い?
たじろぎ、彼を振り仰ぐ。こんな特殊な香りをまとう人など、そうそう、いるものではない。なに? この人は──
(……花火屋さん?)
まじまじ、オフィーリアはジョエルを見た。
彼は片足に重心を預けて「なんか用すか」とかったるそうにザイを見ている。ザイが親指で、こちらをさした。「いや、お前の方が、用があるんじゃねえかと思ってよ」
「は? どういうことすか」
ジョエルは怪訝そうな顔。不機嫌なわけでもなさそうなのだが、口調がどことなくぶっきらぼうで、近づきがたい印象だ。初対面の相手がいるというのに、愛想のかけらもないらしい。ぼさぼさの頭髪とも相まって、何やら、いやにつっけんどん。
オフィーリアは口をつぐんで突っ立っていた。
(……入れない)
蚊帳の外に置かれてしまい、一人つくねんとたそがれる。彼らは二人で、訳のわからないやりとりを続けている──。
すっ、とザイが肩を返した。「じゃ、これで。ごめんください」
その言葉が、急にはっきり耳に届いて、はた、とオフィーリアは我に返る。
「……え?」
一拍遅れて、ポシェットを探った。「あっ──あっ──ちょ、ちょっとザイさん! こ、これっ──これをっ!」
むんずとつかんで、それを引き出し、あわあわ顔を振りあげる。途端、背中が向こうの街角を曲がった。
手紙を持つ手をつき伸ばしたまま、オフィーリアは呆然と取り残された。
昼前に会った時にも、そうだったが、彼はなぜだか、常に、常に、忙しい……。
「あー。あんたがメガネちゃん?」
「──はっ? ど、どちら様ですか?」
ジョエルと呼ばれた若者の、いかにも気安い口振りに、オフィーリアは、くい、と眼鏡をあげる。「ど、どうして、あなた、わたしのことを?」
どこからどう見ても、見知らぬオトコだ。赤いランニングに迷彩パンツ。ぼさぼさの髪をうなじでくくった、どことなくふてぶてしい顔つき。
ジョエルは隠しに突っ込んだ手を出して、くい、と北を親指でさす。「あんた演説ぶったっしょ。きのう、そこの北門通りで」
「……え? あ、はい」
げんなり、ジョエルが嘆息した。
「あのさー。そこは"知りません"」
「は?」
「だから、そこは"知りません"って言っとかないと。誰かにそう訊かれたら、あんたはそう答えなきゃいけない。あの時あんたは北門通りにいなかった。いい? ここんとこ大事だから。そうでねえと死んじまうよ?」
あんた、衛兵に目ぇつけられてんだからさ、とぶっきらぼうな口調で続ける。これだから素人は、とも。
ぱちくりオフィーリアはまたたいた。さっぱり訳が分からない。初対面の相手というのに、不躾に説教されている。さも当たり前のように諭しているが、何度見直しても知らない顔だ。
年の頃は二十代半ば。髪の一本一本が自由気ままに生えているぼさぼさ頭のせいなのか、唇を尖らせる癖があるからなのか、どことなくきかなそうな、やんちゃそうな印象を受ける。
気を取り直し、つい、とオフィーリアは眼鏡をあげる。
「それで、あの、わたくしに何かご用ですの?」
「ああ、そうそう。あんたに教えてほしくてさ」
懐を探って紙片を出し、ジョエルはそれを振り広げる。「黒色火薬は事故が多くて。それで今、ちょっとこういうの考えてんだけど、これがまた、うまく安定しなくてね」
図面? いや、何かの文字だ。計算式?
興味をひかれて紙面を覗き、ふ〜む、とオフィーリアは顎をなでる。
小首をかしげて、紙面の文字を指さした。
「これ、何か持ってくれば、安定すると思うけど──確か前に、何かの本で読んだような──あ、たぶん──弱線薬?」
「低硝化線薬か」
じっと腕組みで思案していたジョエルが、合点したように顔をあげた。
「そうそう、そいつだ!」
ぱちん、と指を打ち鳴らし、オフィーリアの顔をまじまじと見やる。
「やっぱ、すげえな、カレリアの先頭走ってる奴は。ダメ元だったが訊いてみるもんだ。いや、助かった」
「……そ、そう。よかったわ。お役に立てたみたいで」
ぱちくりオフィーリアは瞬いた。でも、この人って確か──
「花火、作っているのよね?」
いちおう念のため確認する。
「そーゆーのも面白くね?」
「……。いや。これでやったら、ものすごいことになると思うけど。これじゃ花火っていうより爆発──」
「いーから。断然おもしれえって。派手な方が」
オフィーリアはまじまじ眺めやる。大真面目なのかと思ったら、
(結構ばかなこと考えてんのね男って……)
ジョエルが「それじゃ」と肩を返した。何事かぶつぶつ言いつつ歩いていく。
足を止め、肩越しに一瞥をくれた。「難易度高いよ? 班長は」
「……班長って?」
ジョエルは指で自分の両目を吊り上げる。「さっき、あんた一緒にいたっしょ? 目つきのキツい、変な喋りかたする」
「ザイさん?」
「あんた、なんで班長がいいわけ?」
ぶっきらぼうにそう言って、面倒そうに嘆息した。「すっげえ物好き。俺なら、ご免こうむるけどな、あんな恐いのが彼氏とか」
「あ、あら。ザイさんは別に恐くなんてっ!」
むしろ、ひょうきん。
「恐い人だよ、あの人は」
そっけなく言い捨て、ジョエルは冷ややかな視線で一瞥する。「あんたは知らないだろうけど」
むっ、とオフィーリアは見返した。
「な、なんで、ザイさんのことを、そんなふうに。あなた、お友だちなんでしょう?」
「てより、仕事仲間だな」
ジョエルは頭をかいて向き直った。「けど、素性も知れねえし。喋んないからね、自分のことは」
オフィーリアは戸惑った。「あの、でも、どうして、わたしに、そんなことを」
「謝礼。あんた、いいネタくれたから。礼は、きちんと、しないと、だめっしょ。じゃ、忠告はしといたから」
言うなり、ジョエルは肩を返した。通りを斜めに横断し、向かいの歩道を歩いていく。
あぜんと、オフィーリアは立ち尽くした。
「……な、なんだったの? あの人は」
ほりほり頬を指で掻く。「悪口、ではなかったようだけど」
彼とは逆の方向に、首をひねりひねり歩き出した。肩越しに彼を振り向くが、その背は、もう見向きもしない。
溜息まじりに目を返し、ふと、道の先に目をあげて、「──おわっ!?」と一歩飛びすさった。
街角の向こうから、ぬっと男が、裸の上体を突き出したからだ。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》