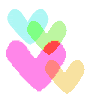
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 4
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「エレーンどこか、あんた知ってるー?」
上背のある裸体の男が、ぬっと不意に目前に迫り、オフィーリアはたじろいで後ずさった。
「……え? え? あの、エレーンのお友だち?」
真っ赤になって口をパクパク、しどもど意味なく辺りを見まわす。突如、壁のごとくに立ちはだかれ、とっさにきょろきょろ逃げ場を探す。男は上半身、布きれ一つまとっていない。まだらなシミのある黒っぽいズボンを、辛うじてはいているだけだ。
長めの髪の、若い男だった。ふわりと柔らかそうな薄茶の髪が目元にかかり、頬はするんとなめらかで、ひげ跡のない顔立ちは、いかつくもなく整っている。色素の薄い瞳が印象的で、もろいガラス細工を思わせる。
ふと、オフィーリアは顔をあげた。「あの、どうして、わたしのことまで知って──」
「あんたのその服ー」
男は無造作に指さした。その先には、領邸から貸与された白襟紺服のメイド服。
つまり、エレーンの元同僚とみなし、居所を知っていると思ったらしい。以前聞いた逗留先を頭の中からひねり出し、オフィーリアはあたふた指をさす。「確か、あの辺りに宿をとったって言っていたようだけれど」
「もう、いないー」
「──そ、そうなんですか」
目前で無造作に身じろがれ、かあっと赤面、上目使いで盗み見た。「あ、あのぉ。もう、お祭りは終わりましたよ? いくら暑くても、街に出るなら、シャツくらいは羽織った方が」
そうだ。なんたるハレンチな。
「やっぱ落ちなくてねー」
「は?」
「ち」
「……ちぃ?」
オフィーリアは愛想笑いで固まった。答えが若干ずれた方から飛んでくるような?
微妙な反応には委細構わず、男はふと、自分の肩越しを振り向いた。
彼の上背で気づかなかったが、どうやら誰かいたらしい。相手にこずかれ、何事か促されているようだ。男が溜息まじりに目を戻した。「悪いんだけど、払っといてくれるー?」
「はい?」
ずい、と後ろにいた者が進み出た。彼と並ぶと、彼の肩あたりまでしか身長のない、小太りの中年男だ。腹に白い前かけを巻いている。近所の飲食店の主といった風情。
店主はしかめっ面で進み出て、くい、と親指で男をさした。
「飯代だよ、こいつの」
ほりほり、オフィーリアは頬を掻く。
「……えーと、それって、つまり」
無銭飲食?
ずい、と店主は手の平を広げて突き出した。
「しめて五千五百カレント。耳をそろえて、きっちり払ってもらおうか」
「ご、五せん──?」
オフィーリアは絶句で瞠目した。店主の顔をあぜんと見返す。「あの、何人分の料金で……」
「客はこいつ一人きりだよ」
だが、昼食代の相場なら、せいぜい一千カレントくらいのものでは?
「さあ、しめて五千五百だ!」
ずずい、と店主は更に詰め寄る。押されて、オフィーリアは後ずさった。
「あんた、知り合いなんだろう? え、どうなんだい。違うのかい?」
知らない。むろん初対面だ。
内心、ぶんぶん首を振る。とはいえ彼は、エレーンの友だち、そう無下にするわけにも──。いやまて。友だちの友だちは友だちではないのか? それならこちらも、無関係とは言い切りがたく──
「……知り合いでした」
観念して、うなだれた。
財布を渋々、ポシェットから取り出す。
(あああ……給料日前なのにぃ〜!)
我が身の不運を呪いつつ、言われるがままに代金を支払う。どうも何気に釈然としないが。
「はい、まいど」
店主はしかめっ面で懐にねじ込み、ぶちぶち言いつつ背を向けた。「もう、すんじゃねえぞハナタレ小僧が。食い逃げしようなんざ、ふてえガキだ」
「……へ?」
ガキ?
あっけにとられて半裸を仰ぐ。「あの、今、何歳かしら」
「十五ー」
頓着なく男は応えた。なんの小細工もない顔で。
しばし、オフィーリアはあんぐり絶句、額をつかんでうなだれた。
「最近の子供って発育いいのね……」
まるで大人並みの体格──いや、彼は背が高いから、今の中年の店主より、下手すれば、よっほど見栄えがする。もっとも、子供だったというのなら、この意思疎通の悪さにも納得できた。言い回しがぬるいというか、会話のピントがずれているというか、受け答えがトンチンカンというか。
話す相手に配慮が足りない、自分本位の話し方。やたらと背の高い、ひょろっと大きなこの外見に騙されたが、話を聞けば、なんのことはない、頭の中身はまだまだ子供だ。とはいえ──。
店主の背を呆然と見送り、たそがれた気分で立ち尽くす。
(……あと、二千カレント)
そして、給料日はまだ遠い……。
大幅に目減りした財源に、げんなり絶望的な気分で額をつかむ。「……ぼく? 今度からは、ああいうお店に入る時には、お財布の中身とちゃんと相談してからにしてね」
十五の半裸は、悪びれたふうもなく頭を掻いた。
「悪いねー。店の人、いつもはおばさんなんだけどー、途中でおじさんに変わっちゃってねー」
「……は?」とオフィーリアは顔をあげる。またも的外れな回答だ。ここは「ごめんなさい」もしくは「もうしません」が通常ではないのか?
とはいえ、反抗しているようでもない。怪訝に十五歳を振り仰ぐ。「なにか違うの? おじさんでもおばさんでも同じでしょ?」
「おばさんは優しいけど、おじさんはそうでもないー」
オフィーリアは眉根を寄せて固まった。彼には何か確たる言い分があるらしいが、意図するところが皆目不明。突っこんで訊けば訊くほど分からなくなるのは何故なのか……。
首をかしげて悶々とする中、十五の半裸はにっこり笑って肩を返す。「じゃあねー」
「ちょおっと待った!」
むんず、とオフィーリアは引っつかんだ。
ズボンの後ろのベルト通しを。
捕獲可能な箇所はここしかないから、微妙な場所だが致し方あるまい。
「なにー?」と十五が、半裸の肩越しに振り向いた。むう、とオフィーリアは顔をしかめる。「白昼堂々そんな格好で練り歩く気? おまわりさんに捕まっちゃうわよ?」
「でも、替えは、今ないしー」
「おうちに戻って着てくればいいでしょ?」
「でも、オレ、ちょっと急いでるしなー」
「こっちに来なさいっ!」
後ろ向きの相手をずりずり片手で引きずって、近くの服屋まで連れて行く。
店頭の吊るしを前にして、オフィーリアはにっこり手を広げた。
「さあ、ぼく? この中から好きな服選んで? 君は背が高いから、大人用でいいわよね。あ、お店の外の、ここからここまでの中から決めてね」
他のはちょっと高いから。
「……あんたってさー」
後ろ歩きで引っ張られながらついてきた彼が、つくづくという顔で向き直った。
「お節介だねー」
「もしかして褒めてる?」
それをいうなら「親切」でしょーが。
「オレ、別にいいのになー」
「こっちがよくないっ!」
そんな淫らな成りで野放しにできるか!?
ここからここまでと限定した吊るしの中から、十五の半裸が選んだのは、白い生地の長袖だった。
あれ? とオフィーリアは振り仰ぐ。「長袖がいいの? こんな真夏に暑くない?」
「風が強いからねー」
「……そ、そお、かしら」
両手を広げて風を見る。無風に近い、そよ風だが。
「夜寒くなるから、どうしようか、って、ホーリーも言ってたしー」
「そ、そう……」
あいまいな笑みを頬に浮かべて、オフィーリアは固まった。風が強くて夜寒い? 己は一体、どこの惑星に住んでいるのだ?
つか、ホーリーってなに。
十五の男子はシャツをはおってボタンをとめると「もらっていいのー?」と振り向いた。溜息まじりに、オフィーリアは手を振る。「いいもなにも、きみ、もう着ちゃってるでしょー?」
「お礼するー?」
「いいわよ、そんなの」
「オレ、何もしなくていいのー?」
十五の男子が驚いたように見返した。「でもオレ、あんたのこと、歓ばすことできると思うよー?」
「あら、ありがと、ぼく。でも、子供は変な気は遣わないの。大丈夫よ、これしきのこと」
オフィーリアは店主を呼んだ。本当は、さっきのお代で目減りして、財布が一気にピンチだが。
シャツの値札は一千七百カレント。おそらく店の価格の最低ラインだ。選定場所を投げ売り数点に限定したのが奏功し、手持ちの金でなんとか間に合う。ちなみに、昼食代より服の方が格段に安いというのが、そこはかとなく腑に落ちない。
「あ、おつり多いです」
ふと気づいて、あわてて言うと、白髪頭の小柄な店主は、老眼鏡をかけ直し、服の値札をすがめ見た。
「おお、本当だ。少し待っててもらえるかの」
よたよた店の奥へと入っていく。
十五の男子は、ぼさっと突っ立って眺めている。いや、のっそりこちらを振り向いた。
「あんた、ばか正直だねー」
むっとオフィーリアは振り仰いだ。
「あのねえ、ぼく。物には原価というものがあるの。きちんと言ってあげないと、お店の人が困るでしょ? 君にはまだ分からないかもしれないけれど」
「ボラレてるとは思わないのー?」
「……え? なに? どういう意味?」
はあ、と十五が脱力したように嘆息した。「おねーさんは、いい人だねー」
高い目線から見おろして、感慨深げにしみじみと言う。
「オレ、あんたみたいな人、けっこう好きかもー」
オフィーリアは引きつり笑った。
「あ、あら。ありがとね、ぼくぅ……」
告白してくれるのは嬉しいが、いかんせん年が下すぎる。君が成人する頃には、お姉さんはいくつだと思っている?
(子供には人気あるのよね……)
なはは、と虚しく笑っていると、十五の男子が「ちょっときてー」と引っ張った。
ひょい、と長身の背をかがめ、よける間もなく覆いかぶさる。
とっさに動くことができない肩に、しわ一つないなめらかな頬が、するり、とたちまち滑りこんだ。頬に何やら柔らかな感触。
……唇?
棒立ちになったその前で、「じゃあねー」と十五歳は踵を返した。
昼下がりの石畳の歩道を、何事もなく歩いていく。
「……じゃ、じゃあねー……」
ぷらぷらオフィーリアも手を振った。
頬に手を当て、その場に突っ立ち、後ろ姿を呆然と見送る。放心状態から、はたと覚め、我に返って脱力した。
「い、今の子って、ませてんのね……」
やがて、ひょろ長い後ろ姿が街角に消えた。オフィーリアも踵を返す。そんなことより、財布の中身が問題だった。強制徴収の飯代と合わせ、しめて七千二百カレント。伴い、財布の残金三百カレント。喫茶店で珈琲一杯、飲んだら終わりの金額だ。給料支給まで、あと五日。これでどうやって乗り切れというのか。
(今月は、三万カレントの本、買っちゃったからなあ……)
内心どんより、肩を落としてうなだれた。こうなったら恥を忍んで、優しいラナを泣き落とす? リナとは違いラナならば、困った時はお互いさまと嫌な顔ひとつせずに貸してくれる。
とぼとぼ道を歩きつつ、ぶつぶつ己に言い聞かせる。いや、あれは立て替えなのだ。あの子がエレーンの知り合いならば、エレーンに返済させれば済む。本人も商都にいることだし、明日にでも取り立てにいけばいい。いやだがしかし、おちゃらけ女エレーンが、素直に払うと言うだろうか──。
むむ、とオフィーリアは顔をゆがめた。「えー。あたし、そんなの知らないわよぉー」とか口を尖らせて反論し、じたばた往生際悪く逃げまわる気がする。いくら考えても絶対確実にそうなる気がする。となると、
(一トラスト近く丸損てことに……)
情け容赦のない現実に、くらり、と気が遠くなった。それだけあったら、最高級の辞書が買えるではないか……。
「──それにしても」
昼下がりの道に、人けはない。ひっそり静かな街の通りに視線をめぐらせ、オフィーリアは釈然としない思いで首をかしげた。
街を歩いていて出会ったのは、又もエレーンの知り合いだった。この通りが異民街に近いという事情もあろうが、この短時間に三人となると、偶然では片付けられない何かを感じる。
なぜ、エレーンの知り合いばかりが街をうろついているのだろう。気だるい祭の翌日というのに。まして暑い日中に。道往く人影もまばらな時刻に。もしや散歩が趣味だとか? それにしたって、そろいもそろって遭遇頻度がいやに高い。いや、そもそも彼らは何者なのだ?
友人というには無理があるから、おそらく用心棒の類いだろう。あんなふうでもエレーンは領家の奥方さまだから。最初に会った知り合いなどは──彼女が女子会に連れてきたあの無礼な長髪などは、いかにも柄が悪かったし、目つきもどことなく鋭かった。態度もがさつで横柄だし、口も悪くて最悪だった。だから美形にもかかわらず、出会ってものの三秒で、あの場の女子全員を敵に回すことになったのだ。
すっ、と目端を色彩がよぎった。
追い求めていた色と輪郭──はっと思考を中断し、オフィーリアは顔をあげる。
「ザイ、さん?」
あわあわ動揺、立ち尽くす。なんということ、本日三度目!
ぐぐっ、と歓喜に拳を握る。やはり、運命の含意を感じる。大いなる黙示!
いかにも彼が、街角にいた。
舗道の先の、次の次の曲がり角。だが、じっと動かないのは何故なのか。
彼は壁に背をつけて、道の先をうかがっているように見える。もしや、隠れんぼでもしてるとか?
はた、とオフィーリアは我にかえり、ポシェットの中をあわててさぐった。
「そ、そんなことより手紙……あの手紙、今度こそ渡さないと……」
なぜだか理由は不明だが、彼はたいそう忙しい。うかうかしていると、すぐに消えてしまうのだ。
むんず、と手紙を引っつかみ、彼がいる二区画先へと足を踏み出す。
「ザ──っ!」
言いかけ、はっと口を押さえた。
彼とはまだ距離がある。迂闊に声などかけたりすれば、又どこかへ消えやしないか? いつも何かと忙しい彼は、今、目の前にいたかと思えば、するりとどこかへ行ってしまう。捕まえようとする腕を、あたかもすり抜けていくように。
よおし! と密かに気合いを入れた。ならば、腕なりシャツなり、まずは、この手でつかんでからだ。
口を押さえ、くすくす忍び笑いで足を運ぶ。
「……鬼ごっこの続きみたい」
後ろから脅かしたら、どんな顔をするだろう。
──忙しいんで。
なんの関心も示すことなく、彼は頓着なく立ち去ろうとした。だから、みんな興味をひかれ、後をついていったのだと思う。内心おっかなびっくりで。この制服に媚びぬ者がいたとは、正直驚きだったから。
世の若い男性は、この制服を目にした途端、下出に出るか卑屈になるかのどちらかだ。彼らはたいてい頼りない。だが、彼はそうではなかった。
彼はすることなすこと、そつがなかった。子供に教える教師のように他人を扱い慣れている様子で、無難にやり過ごそうとしているのがわかった。だが、そう振るまえば振るまうほどに、彼が逃げれば逃げるほど、皆、矜持を刺激されたのだと思う。だって、彼がなびかないから。そんな異性はいなかったから。
いつの間にか、夢中で彼を追いかけていた。鬼ごっこの街角で、後ずさりする彼の背を見つけて、無我夢中でしがみついた。振り向いたあの時の、彼の驚いた顔が忘れられない。
運命だと思った。
みんなが彼を追っているのに、彼と巡りあったのは、ただひとり自分だけ。この人は、きっと運命の人だ──。
驚いて振り向いた、薄茶の髪の輪郭が、日に透けて、きれいだった。
だから、一瞬で恋に落ちた。
足音を忍ばせ、見つからないよう、一歩、一歩、慎重に進む。
街角にひそんだ彼の背が、いよいよ近付き、視界に迫る。馬車が二台すれ違うことができるくらいの道幅だ。日ざしをさえぎる高い石壁に囲まれた、異民通りの石畳の道。その道の右手にいる。彼はなぜか、道の先をじっと見つめ、一瞬たりとも目を離さない。
声をかけようと口をひらき、ふと、オフィーリアは視線をそらした。
視界を何かがよぎった気がする。彼から更に三つ先の街角。あれは、背の高い人影──?
(え、あのシャツって)
今しがた買い与えたシャツだった。ならば、あれは、少し前に店先で別れた、あの十五の欠食児童?
だが、人影は大通り方面に向かったが、十五の彼が立ち去ったのは、それとは逆の西の方角。なぜ、あんな所をうろついているのか。落とし物でも探している? もしや、なにか困ったことでも──いや、今は時間がない。あの子のことはひとまず置いて、意中の彼を捕まえるのが先決だ。
そうだ。今度こそしっかりと、彼をこの手で捕まえるのだ。そうしないと、するりとすり抜けてしまうから。どこの誰にも束縛されない、自由な風であるかのように。
「ザイさんっ!」
勇気を出して声をかけ、はしゃいで後ろから腕をとる。
彼の肩が、鋭く震えた。
肩をそむけた全身が、ぴたりと動きを停止する。己の身に何が起きたか、目まぐるしく推量しているかのように、強ばった背は動かない。
向こうを向いたままの横顔から、は……と小さな吐息が漏れた。
それまで忘れていたような呼吸が戻り、静かに彼が振り向いた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》