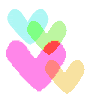
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 5
( 前頁 / TOP / 次頁 )
わずかに目を細めただけで、ザイの表情に変化はない。だが、視線は冷たく、異様に鋭い。
オフィーリアは足がすくんで動けなかった。唇の端がわなないて、膝頭が止めようもなく震えていた。何も身に覚えはなかったが、訳がわからないながらも、はっきりと悟った。自分が何か、とんでもない過ちを仕出かしたのだ、ということを。
ザイがおもむろに振り向いた時──肩から強ばりが抜けたあの時、ようやくオフィーリアは気がついた。彼がどれほど気を張っていたか、どれほどの緊張を強いられていたのか。
ザイは街路に立ったまま、未だ口をひらかない。飄然ととぼけた普段の気安さはそこになく、研ぎ澄まされた切っ先のような、触れれば切れそうな剣呑さだけが、しんと冷ややかにそこにあった。
その様子に気を呑まれ、オフィーリアはおどおど目をそらす。沈黙に不気味さを覚えたのは、これが初めてのことだった。ただならぬ視線が向けられていることに、それが他ならぬ自分に向けられていることに、少なからず困惑していた。「怖い人だ」と彼を評したジョエルのぶっきらぼうな忠告を、思い出して実感する。とりなそうにも混乱するばかりで何が起きたか判然としないが、理屈ではなく本能で、それを感じとっていた。全く未知なる領域に意図せず踏みこんでしまったことを。一言でいうなら、おそらくは
"危険"を。
ゆらり、とザイが身じろいだ。
体の脇に下ろした指が、彼のかたわらで、すっと動く。
びくり、とオフィーリアは硬直した。
空気が不穏に張りつめていた。背筋が凍り、すぐにも逃げ出したい衝動に駆られる。だが、オフィーリアはそこにいた。我慢して踏み止まっているわけではなかった。足がぴくりとも動かせないのだ。
凝視したままの足元で、街路の上の靴先が踏みだす。
ぎゅっとオフィーリアは目を瞑った。一体自分は何をしたのか焦って思考をめぐらせるが、何ひとつ理由が思い浮かばない。想像さえつかなかった。どんなに細かく思い出しても、今、自分がしたことといえば、ただ「後ろから声をかけた」だけだ──
ふっ、と空気がゆるんだ気がして、オフィーリアは恐る恐る目をあげた。
ザイの注意がそれている。街角に視線をめぐらせ、耳を澄ましているようだ。すがめ見るように目を凝らし、横顔は何事かうかがっている。
道端のごみを、黒い鴉が漁っていた。大きな祭の翌日とあって、裏通りの店先の大半には「本日休業」の札がかけられ、どこも鎧戸を下ろしている。
ザイは無言で逡巡し、やがて身じろぎ、目を戻した。
壁にもたれて腕を組む。
「あんた、あいつと知り合いで?」
少しかすれてはいるが落ち着いた声。その口振りに気負いはない。いつもの彼だ。
膝からへなへな力が抜け落ち、オフィーリアはあわてて踏み止まった。彼からの思わぬ問いに、しどもどしながら首をかしげる。「ど、どなたのことですか」
「あんたが逃がした、あのガキですよ」
今しがた通りを横切った欠食児童のことらしい。
「に、逃がすだなんて、そんなつもりは──」
「ま」
投げやりな調子で言い分をさえぎり、ザイは疲れたように目頭を揉んだ。「今となっては、もう、どうでもいいことですがね」
何が起きたか皆目わからず、オフィーリアは視線を泳がせた。「す、すみませんでした。わたし、あの……」
口調こそ普段の彼に戻ったが、彼はまだ怒っている。巧みに本音を隠してしまうが、こちらを眺めやる冷めた視線に、組んだ腕の指先に、ひしひしとそれを感じた。そして今、務めて怒りを押し殺そうとしている。
ためらい、オフィーリアは唇を噛んだ。ここで会釈し、辞去してもよかった。そうすれば、とりあえず、この気づまりな状態からは解放される。けれど、ここまで踏んばれたのは奇蹟のようなものなのだ、なんとしてでも挽回したい、そんな気持ちも働いた。それで前にも後にも動けずにいる。
いくつか通りを隔てた先の、閑散と続く建物の狭間で、人影が途方に暮れたように天を仰いだ。なにぶん遠目でしかと見分けることはできないが、日陰になった石畳にいるのは、どこかで見たような若い男だ。
ザイが身じろぎ、持て余したように嘆息した。「しなけりゃならないことがある。時間が惜しいんですよ」
「な、何か、お役にたてることがあればっ!」
オフィーリアは弾かれたように顔をあげた。とっさに飛び出た言葉だったが、その気持ちに偽りはない。ザイは面倒そうに振り向いて、いかにもぞんざいに言葉をほうった。「俺の役に立ちたいってんですか?」
「は、はい! わたしにできることなら何でも──」
「なら、消えてくれませんかね」
オフィーリアは顔を強ばらせ、きゅっ、と口を引き結んだ。「……そんな、こと」
つぶやき、顔を振りあげる。
「そんなこと言わないで! お願い、きっと役に立つから!」
「俺は、女子供は信用しない、と決めている!」
びくり、と肩が大きく震える。
呆然としたまま瞬いて、オフィーリアは視線をさまよわせた。「……でも、わたしは」
「勘弁してもらえませんかね。賢しらな女は苦手なんスよ」
困ったような吐息が聞こえた。
力が抜け落ちた手を握り、オフィーリアは浅く息をつく。
「わたし、こんなちんちくりんだけど……だから、せめて頭だけでもがんばろうと思って……でも、努力しますから。みんなみたいにかわいくなるから。あなたが嫌なら、眼鏡もやめる! だから──」
「誇りのない女は嫌いでね」
ザイはけんもほろろに一蹴した。
オフィーリアは唇を噛みしめる。「あなたのそばにいたいんです。もう邪魔はしないから」
「たく、わからねえ女だな」
ザイが疎ましげに舌打ちした。
ひときわ大きく息を吐き、舌打ちまじりで、ぼそりとごちる。「あんたみたいなのは手に負えねえよ」
オフィーリアは息を呑み、言葉もなく瞠目した。
震える息を浅くつき、うつむき、奥歯を食いしばる。「……でも、わたしにできることって、他には何も」
「この期に及んで、まだ役に立ちたいってんですか」
辟易としたように目をそらし、ザイが大きく息を吐いた。振り向きざま、オフィーリアの手首を引っつかむ。
「だったら、これから、どこぞの宿で、憂さでも晴らさせてもらいましょうか」
無我夢中で手を払い、わき目もふらず駆けだした。
閑散とした街路の石畳を、オフィーリアはやみくもに駆けぬけた。
『なら、消えてくれませんかね』
ガンガンうち鳴る頭の中で、彼の声が反復していた。感情もこもらない乾いた声。なんの容赦もためらいもない──。
彼に娼婦のように扱われたことが、そんなふうにしか見られていなかったその事実が、オフィーリアの心を打ちのめした。つくづく思い知らされていた。その程度の存在だったと。いくらでも代わりのいる、声を荒げる価値さえない、
──彼にとって、この自分の存在は。
胸に慟哭がつきあげた。
だが、無理にそれを飲みこんだ。いくら人けがないとはいえ、街中で泣きだすわけにはいかない。
だしぬけに、腕がとられた。
とっさに足がつんのめり、反動で体が振りまわされる。
あわてて後ろを振り向くと、あの彼が立っていた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》