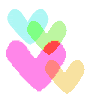
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 6
( 前頁 / TOP / 次頁 )
気だるい夏日を、あの禿頭がさえぎっていた。
引きしまった肩にランニング、高い身長、細い腰。そして、
「どうしたんすか」
心配そうに覗きこむ、あの黄色い丸眼鏡。
「……セレスタン、さん」
オフィーリアはうろたえ、顔をそむけた。
のほほんと穏やかなあの彼だった。背丈があって人並よりも大きいくせに、態度は存外にていねいで、殊のほか親切で礼儀正しい。背をかがめて話しかけ、一緒に眼鏡を選んでくれた──。彼らの仲間には他にも会ったが、この彼も付近をうろついていたのか。
下ろした手の先をぎゅっと握って、殊更に彼から顔をそむける。こんな時に、誰とも顔を合わせたくなかった。どこから追ってきたのだろう。いつから見ていたのだろう。刹那かいま見た彼のいぶかしげな表情は、明らかにおかしいこちらの様子を見咎めたに違いなかった。
あの辛らつな言葉がよみがえり、不意に目頭が熱くなる。やにわにこみあげた塊を、あわてて押しこみ、飲みこんだ。「な、なんでもないです。大丈夫ですから」
「だったら、なんで泣いてんです」
静かな声で指摘され、はっとオフィーリアは頬をぬぐった。
殊更に背を向けたまま、片手で強く口元をつかむ。すぐにもこの場を立ち去りたいが、手首がまだつかまれていた。やんわり振り解こうとするものの、大きな手は外れない。事情を一通り説明するまで、手を解くつもりはないらしい。
オフィーリアは観念した。小さく息を整えて、務めて平静な声を作る。「本当に、なんでもないんです。わたし、ザイさんを怒らせてしまって」
「あいつに何か言われたんすか?」
「……わたし、は」
無残な有り様が脳裏をよぎり、オフィーリアは喉を詰まらせる。
たまらず目を伏せ、うつむいた。胸に去来した思いの苦さに、顔がゆがみ、唇が震える。必死で歯を食いしばるが、涙が頬を滑り落ちてしまう。
オフィーリアは力なく首を振った。「……やっぱりだめ。わたしなんか冴えないメガネで。みんなみたいにかわいくなくて。だから……」
「あんたは、かわいいすよ」
「嘘っ!」
とっさに叫んで言い返し、強く強く首を振る。
「そんなこと思ってないくせに!」
セレスタンは無言で立っている。背を向けたままなので、彼の表情は見えないが、さすがに呆れてしまったのだろう。案の定、手首をつかむ彼の手が離れる。
すっ、と腕が左右から伸びた。
「あんたはかわいいすよ、オフィーリア。素直で、無邪気で、まっすぐで。いつも一生懸命で」
オフィーリアは瞳を潤ませたまま困惑した。
彼の大きな手の平で、左右の肩をすくいあげられていた。顎の下で腕が交差し、つむじに軽く、彼の顎が押し当てられている。
後ろからすっぽり、体ごと抱えこまれていた。覆いかぶさった大きな気配に、おどおど視線を泳がせる。「で、でも、わたしは、こんなふうで……だから」
「いい女すよ、あんたは」
街路の石畳に目を据えて、オフィーリアは返事をしなかった。小さな子供を慰めるように、柔らかい口調で彼は続ける。
「あんたが泣くことはありませんよ。あんたはそんなにかわいくて、あんなに賢く、正直じゃないすか。あんたはあんなに優しいじゃないすか、街をうろつく裸のガキを、見捨てておけやしねえほど」
服を買い与えた少年の、邪気ない声が脳裏をよぎった。
『オレ、あんたみたいな人、けっこう好きかもー』
頓着のないその好意に、胸が詰まり、顔をゆがめる。
「ねえ、オフィーリア。あんたの誠実な人柄は、信用と賞賛に値する。これは大事なことですよ」
いっそ、ふさいでしまいたい耳元に、落ち着いた声が優しく届いた。心遣いは痛いほどわかった。ずたずたに打ち砕かれた矜持と自信を、取り戻させようとしてくれている。けれど、返って辛かった。
オフィーリアは強く瞼を瞑る。なぜ、いつも、こうなのか。なぜ、うまくいかないのか。いつだって、いつだって、そうなのだ。なぜ、いつも報われないのか。特別な相手に向けた想いは、
──なぜ、いつも届かない。
噛みしめた顎がわなないた。ぼろぼろ涙がこぼれ落ちる。
うつむいた顔を両手で覆い、オフィーリアは声をあげて泣きだした。
目をこすり、子供のようにしゃくりあげる。ただ泣くことしかできなかった。泣いてもどうにもならないことも、ここが街中であることも、頭の中ではわかっているのに。
「……あの野郎」
やがて、腹立たしげな吐息とともに、大きな手の平が頭に置かれた。「俺がぶん殴ってやりますよ」
「──だめ!」
目をみはり、オフィーリアは首を振った。「やめて! ザイさんは悪くない!」
「じゃあ、あんたが悪いの?」
ひるんで背後を振り仰いだ。
頬を伝った涙の雫を、セレスタンは指の先で払う。
「そうじゃないでしょう。今のは奴が悪いすよ。ガキみたいに癇癪起こして、あんたに八つ当たりしたんすよ。あんたのしたことに他意はない。あんたは何も悪くない。当たった相手が悪かったんすよ」
たまらずオフィーリアは目をそむけた。包みこむ腕をがむしゃらに押しやる。「は、放して。もう、平気ですから」
「ザイは、白馬の王子様なんかじゃないっすよ」
もがく肩が凍りついた。
セレスタンは軽く息をつき、言って聞かせるように言葉をつむぐ。
「あいつは難しいんすよ男でも。何考えてんだか、わからねえとこありますし。奴とつるんでられるのは、俺くらいのものですよ。だから、あんたは、もう関わらない方がいい。追っても傷つくだけですよ」
わななく唇を噛みしめて、オフィーリアはじっと石畳を見つめる。
「ザイは無駄に情けをかけない。埒外の相手は、平気で切り捨てる奴ですよ。邪魔になれば、排除する。躊躇もしなけりゃ動じもしない。あんたにはもっと、真っ当な男がお似合いですよ」
長い腕が、ゆるりと解かれた。
肩に軽く手が置かれ、温かな気配が、すっと離れる。「じゃあね、メガネちゃん」
「──まって!」
オフィーリアは顔を振りあげた。
「ひどいことしないで」
セレスタンが面食らった顔で動きを止めた。オフィーリアは必死で訴える。
「ザイさんのこと殴ったりしないで。大事な人なの。大切な人なの。お願い──お願い!」
セレスタンは眉をひそめて見ていたが、やがて手をあげ、踵を返した。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》