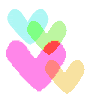
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」2 ──第2部5章 11話 「岐路 」7 から分岐
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「──セレスタン。まあた、お前かよ〜」
寝台で雑誌を見ていたバパは、セレスタンの顔を見るなり、もそもそ上掛けにもぐりこんだ。「俺は今、眠いの」
相手の顔つきを見ただけで面倒事と察したらしい。
「そんな殺生なこと言わないで、力貸してくださいよ。ねっ、頭(かしら)?」
バパに取りつき、セレスタンはゆさゆさ肩をゆする。
ザイと彼女の仔細を説明。三度の飯より噂好きな首長のこと、すぐにも乗り出してくるだろう。
ちら、とバパは横目で見た。そして、あくび交じりで背を向けた。
「ほっとけよ」
「……え?」
セレスタンは拍子抜けして、またたいた。意外にも、シーツに逃げこみ、出てこない。
「もー。いつになく薄情じゃないっすか〜。ねえ、かしら〜」
引っぱられたシーツを引っぱり戻して、バパは更に潜りこむ。「だから、ほっとけって。そういうのはな、傍がいじっちゃいけねえんだよ」
「ウォードの時には、相談に乗ってやってたじゃないっすか〜」
「あいつはまだ、ガキんちょじゃねえかよ」
バパは面倒そうにあくびする。「別にザイから相談もちかけられたわけでもあるまいによ。口説き方も、連れこみ方も、万事あいつは心得てんだろ? だったら俺の出る幕はねえよ」
手だけを出して、ひらひら振る。はい、終わり、というように。
「だからぁー。そういう下世話な話じゃなくてすねー」
セレスタンはやれやれと腕を組む。「言ったでしょ? メガネちゃんはもっと、うぶでまっすぐな女の子なんすよ。男と接した経験なんて、きっと全然ないんすよ。それが、いきなりザイですよ? あの毒舌で苛められたら可哀相じゃないっすかー。頭(かしら)だって、親として責任感じるでしょー?」
「んー……ない」
中身をはしょった雑な返事に、セレスタンは口を尖らせた。
「そんなにザイが恐いんすか?」
「そんなことは言ってないだろ?」
むっくり、バパは起きあがる。
「なら!」
「でもダ〜メ」
ごろり、と再び横になる。
「──ねえー。かしらぁ〜」
「大丈夫だよ。奴だって、いつまでもガキじゃねえんだからさ」
「ザイをガキだなんて思ったことは、一度だってありませんよ」
セレスタンは白けて嘆息する。
腕枕で寝転んで、バパは小さく苦笑い。「俺から見れば、まだまだガキだよ、ザイの野郎も、お前もな。──しかし、あのザイが色恋沙汰とはな。いやはや青春って奴だねえ」
「ま〜た、そんな他人事みたいに」
「ん? だって他人事だろ?」
「頭(かしら)も早く体治して、よろしくやりゃあいいじゃないすか。知ってんすよ? 飲み屋に行くたび、店の女に言い寄られてんの。商都で待機なんて好遇は、めったにあることじゃないっすよ」
腕枕の横顔で、バパは困ったように苦笑いする。「……いや、俺はいいよ」
「ねえ、頭(かしら)、らしくないすよ」
相変わらずのその様に、セレスタンは嘆息した。「聞いてましたよ、頭(かしら)の噂は。一人でシマ張ってる頃は、派手に遊んでたようじゃないっすか」
「──ああ。ずいぶん馬鹿もしたっけな」
背を向けたまま、バパは応える。
だが、それきり口をつぐんでしまった。この話になると、いつも、こうだ。
「もう、いいじゃないっすか」
その態度にたまりかね、セレスタンは思いあまって顔をあげた。
「義理は十分果たしたでしょうに。トレイシーさんが亡くなったのは、もうずいぶん昔でしょう」
「──あいつには」
じっと寝たふりを決め込んでいたバパが、ふと目をあけ、口をひらいた。
「トレイシーには、金さえ届けりゃ文句はないだろうと思っていた。あの頃の俺ときたら、賭場に顔を出しては飲み歩き、夜ごと女を取り替えて、長らく家にも帰らなかった。
あいつは何通も手紙を寄越した。だが、ろくに目も通さなかった。中身はどうせ知れているからな。細々とした近況と、いつ帰るのかって催促だ。一度も返事は書かなかった。油断をしていたんだよ。一度手に入れれば俺のもの、未来永劫なくなりはしない──今にして思えば、とんだ独りよがりだが。
その手紙もふっつり途絶えて、さすがにヤバイと家に戻った。だが、巷でよく言うように、ものの価値は失くして初めて気づくんだよな。まったく俺は傲慢で、とんでもなく迂闊だった。まるで思いもしなかったんだよ、別の女とよろしくやってるその時に、虫の息の死の床で、俺を呼んでいたなんて」
「……頭(かしら)」
思わぬ話に、セレスタンは言葉を失う。それに気づきもせぬように、バパは続けた。
「戻った時には、家はすっかり片付いて、あいつの姿はどこにもなかった。結局俺は、女房の死に目に会えないどころか、葬儀にさえ間に合わなかった。なにせ俺が戻ったのは、それから二年も後だからな」
「……ずい分長く、会ってなかったんすね」
「それでも、想像が、ついちまうんだよな。あいつがどんな顔で、あの手紙を書いていたか。どんなふうに椅子に腰かけ、どんなふうにペンを握り、どんな顔で物思いにふけって、窓から空を見ていたか。毎日部屋を片付けて、窓辺の花瓶に花を飾り、通りの先を戸口からながめて、一日に何度も、日が暮れるまで──」
──ねえ。いつになったら、戻ってくるの?
彼女の遠い後ろ姿に、バパは眉をしかめて目を閉じる。
ふと、我に返ったように身じろいだ。
「悪い。湿っぽい話になっちまったな」
黙り込んだ相手に気づいたらしい。さばさば声を切り替える。
「なんにせよ、ザイにはザイの考えがあるさ。お前も野暮な真似はするんじゃねえぞ」
ふと、セレスタンも我にかえる。「──あ、でも、ザイの奴、ほっといたら、ひどいこと言いそうな気がして」
「それならそれで仕方がないだろ。乗るも逸れるも当人二人の問題だ。血反吐はくような眠れぬ夜も、押し潰されそうな後悔も、生涯当人が背負うんだ。だからなセレスタン、そういうものは、肩代わりできない赤の他人が無闇にいじっちゃいけねえんだよ」
「でも、俺は──」
「いいから、お前も手を出すな。ザイにも、そのオフィーリアちゃんにも」
「──え?」
ぽかん、とセレスタンは見返した。「……ねえ、かしら?」と己を指さす。
「俺、言いましたっけ? メガネちゃんの名前」
さわり、と窓辺で梢がゆれた。
遠い路地から、怒鳴り声。
「……なんか腰が、痛くてよ〜」
そろり、とセレスタンから目をそらし、バパはもそもそシーツを被った。
密かに気を揉んでいたらしい。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》