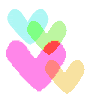
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 8
( 前頁 / TOP / 次頁 )
ミモザの無残な残骸が、道ばたに寄せられ、積まれていた。
舗道を行き交う車輪の音に入りまじり、人足の荒っぽい声がする。祭で使った大掛かりなオブジェを解体している作業員だ。それで出た残骸を、いく台もの荷馬車に積みこんで、街の外へと運び出している。
大通りにある時計塔広場。その水しぶきをあげる噴水の縁に、オフィーリアは座りこんでいた。
矢も盾もたまらず異民通りから逃げ出して、真昼の街をさまよい歩いた。そして、どこをどう歩いたものか、気がつけば、人けない裏通りを抜け、この大通りにさまよい出ていた。
うなだれ、オフィーリアはしゃくりあげる。彼の言葉が胸にこたえた。
『 賢しらな女は苦手なんスよ 』
泣きはらした目をハンカチでこすり、握りしめた眼鏡をポシェットの中にしまう。
噴水の縁から立ちあがり、周囲に視線をめぐらせた。
街の輪郭が、途端にぼやける。あわててポシェットに手をかけた。その口をあけようとした指先を、はっとして引きとめた。まだ、何も始まっていない。このままでは何も始まらない。
濃霧の中にいるように、街の輪郭はぼんやりしていた。だが、ここでくじけたら、ずっと、ずっと、このままだ。
きゅっと唇を引き結び、オフィーリアは顔をあげる。濃霧の中に目を凝らし、手探りしながら歩き出した。
かたわらの車道から、ガラガラ車輪の音がした。視界がひどく悪いので、耳から入る音だけが頼りだ。
濃霧の中で、色彩がぼんやりうごめいていた。あれは人だろうか。それとも野犬? そうでなければお店の旗……?
目を凝らしても、輪郭さえも、はっきりしない。ついつい眼鏡に手が伸びた。
「う、ううん! だめよっ!」
甘い誘惑を振り払い、オフィーリアは首を振る。
──慣れなければ。
壁を指先で叩きつつ、一歩一歩、踏みしめる。
今日は、練習をするにはうってつけだった。暑い盛りに、祭の翌日という事情が重なり、街には珍しくひと気がない。裸眼では少しづつしか進めないが、のろのろ歩きをしていても、これなら誰かに突き飛ばされたり、押しのけられる心配はない。何かで急ぐ人たちや、よそ見をしている人たちに。
なんとしてでも眼鏡なしに慣れなければならない。眼鏡がなければ化粧も映えるし、髪だって毎晩巻いて、おしゃれな店でお喋りして──
外灯や街路樹を探りつつ、一歩一歩、慎重に進む。足元が心許なく、つまずきそうになるけれど、その都度なんとか持ちこたえた。今日はこのまま眼鏡なしで、寮の部屋まで帰りつきたい。
だが、それには一つ難関がある。領邸のある北街区へ戻るには、北と南の街区を隔てる北門通りを渡らねばならない。北門通りの西端には、街道に続く北門があるため、正門付近ほどではないにせよ、荷馬車の交通量が案外多い。だが、それさえやり過ごすことができたなら、領邸のぐるりを囲む遊歩道に入ることができる。
よろめきながらも、地道に歩いた。
四苦八苦しながら、それでもようやく慣れてきた頃、舗道を走る車輪の音が、これまでよりも大きくなった。この大通りと交差する北門通りが近づいているのだ。
さすがにオフィーリアは怖気づいた。
街路樹につかまって足を止め、眼鏡を入れたポシェットに、ためらいがちに手を伸ばす。口をあけ、袋の中に眼鏡を探った。視界がほとんど利かないのに、このまま車道を突っ切るのは、無謀を通り越して自殺行為だ。せめて、北門通りの交通量と、付近を走る馬車の位置くらいは、確認しておいた方がいい。
しばらくぶりの眼鏡をかけて、オフィーリアは面食らった。音が大きくなったから、車道は目前だと思っていたが、実際は、まだ少し手前の位置だった。歩道の左手の店舗で数えて二軒先というところ。
眼鏡をかけて明瞭になった視界には、やはり誰もいなかった。昼の歩道は閑散として、この辺りにも人けはない。
オフィーリアは交差点を眺めた。北門通りは交通量の差が激しい。くる時には続けざまにやってくるし、こない時には、全くこない。
大通りの後ろの方に、交差点へ向かう荷馬車がいた。今は作業の途切れ目らしく、動いている荷馬車はそれ一台きりだ。北門通りにも行き来はなく、石畳の舗道はがらんとしている。
後ろの荷馬車が左折してしまうのを少し待ち、周囲の配置を目に焼きつける。
オフィーリアは眼鏡を外した。大丈夫。馬車はすっかり途切れている。しばらく、やってこないはずだ。
手探りで、再び地道に歩く。知らず知らず気が急いた。知らぬ間に早足になってしまっている。いや、焦らずとも大丈夫。馬車がいないのは確認した。車輪の音も聞こえない。今のうちに通りを渡ってしまいたい。
不意に明るく、視界がひらけた。
ついに、北門通りの歩道に出たのだ。
思わず足を止め、深呼吸した。踏み出すには、やはり勇気がいる。
ためらい、オフィーリアはうつむいて、きゅっと唇を引き結ぶ。黄色い眼鏡の優しい彼は、ああ言ってはくれたけど、
「──でも、やっぱり、わたし、きれいになりたい」
顔を振りあげ、踏み出した。
転ばぬように慎重に、けれど、心もち早足で、一歩、二歩、三歩。馬鹿なことをしていると、自分でもわかっている。けれど、それでも、少しでも小賢しく見えなくなるなら──。
胸がどきどき高鳴った。ひらけた舗道が強い日ざしを反射して、辺りは一面まっ白で、何が何やらわからない。耳元の鼓動がうるさくて、だんだん頭がぼうっとしてくる。──いや、怖がることはない。それほど長い距離じゃない。いつも何気なく、無造作に渡っている、渡り慣れたあの道だ。怖がることなど何もない。ただほんの十数秒、足を交互に出しさえすれば、それで向こうに辿りつく。さあ、早く渡ってしまおう──
どん、と背中に、何かが体当たりするようにぶつかった。
角張った車体の残像が、刹那、大きく視界をよぎる。
爪先が地面から離れた。
止めようもなく体が浮き、直後、激しく叩きつけられる。
意識が、彼方へ消し飛んだ。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》