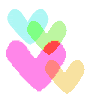
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 11
( 前頁 / TOP / 次頁 )
邸内に配された豊かな樹木が、夜闇に黒々と広がっていた。その中を、幅の広い馬車道が、ゆるく、長く続いている。
夕刻の鐘とともに閉門し、馬車の行き来が途絶えると、正門と裏手をつなぐ車道には、およそ人けというものがない。
しん、と静まった月下の道を、オフィーリアはとぼとぼ歩いていた。
白く浮かびあがった石畳の先に、寮の窓が明るく見えた。夕涼みでもしているのか、襟元をゆるめた二人連れが、壁ぎわを気負いなく行きすぎる。一日の終わりの見慣れた光景。
耳になじんだ館内のざわめきが思い浮かんで、オフィーリアは足を止めた。
ためらい、右手に道を折れる。
「……みんなが部屋に引きあげるまで待とう」
今は、誰とも会いたくない。
ぽつんぽつんと外灯が、わびしく脇道を照らしていた。小奇麗に整った道の先まで、ひっそりとして、誰もいない。
外灯だけがぼんやり灯る、白々として人けない道を、オフィーリアはひとり、とぼとぼ歩く。この広い敷地内には、大型の施設がいくつかある。そして、それらを所有するラトキエ領家は、それらの一部を開放し、敷地内の見学を受け入れている。もっとも今は緊急時で、そのあらかたを閉鎖しているが。
前方がひらけて足を止め、オフィーリアは道の先を仰ぎやった。建物の四角い陰影が、夜空を背負って佇んでいる。
この瀟洒な煉瓦造りは、古今東西の資料を集めた、この国随一の資料館だ。ここは一般には非公開だが、領邸関係者、おもに官吏などが利用するため、ここならば、あいているはずだった。
正面玄関に足を向け、ガラス扉のノブを引く。
オフィーリアは溜息をついた。
「……閉まってる、か」
念のため、建物左手の外階段にまわってみる。閲覧室のある二階に続く階段は、劇場の正面にあるような、段差の低い、五人横並びで歩けるほどに幅の広い石段だ。
白石の階段を踏みしめて、頭上のひらけた踊り場に立つ。
金のノブに手をかけて、オフィーリアは溜息をついた。
「……ここも、だめか」
やはり鍵がかかっていて、館内には入れない。ガラス戸の向こうを透かし見れば、館内は無灯で、ひっそりしている。寮から見る資料館の窓は夜遅くまで明るいため、あいている印象があったのだが、領主が不在で利用がないのか、早目に閉館したらしい。
「……ついてない」
オフィーリアは肩を落として階段を降りた。
地面まで数段を残して足を止め、のろのろ石段に腰をおろす。星々がまたたく空の下、静かな夏虫の音を聞いていたら、不意に涙が込みあげた。
もう、すっかり嫌になり、膝をかかえてうつぶせる。本当にとことんついてない。今日は人生最悪の日だ。頬を張られたような荒っぽい怒声が、まだ耳の奥に残っている。
『ばかやろう! なにやってんだ!』
意識が途切れる寸前に、耳に飛びこんだあの罵声。
ショックだった。あんなふうに、御者に怒鳴られたのは初めてだ。
気がつくと、月光射しこむ窓辺の長椅子に寝かされていた。灯りのない薄闇の中、眼鏡を探して見まわせば、きちんと片付いた部屋だった。
見覚えのある簡素な事務室。男声のやりとりに気がついて、ひらいた戸口に目をやると、紺の制服の後ろ姿があった。よく見る制服。立ち働いていたのはラトキエ領邸の門衛たち。
領邸正門にある詰め所だった。だが、自分は確か、通りで馬車にはねられたはずだ。それがどうして、こんな所で寝ていたのだろう。
様子を見にきた白髪頭の同僚に、おそるおそる尋ねると、彼らが保護してくれたのだという。飲み物を手にして戻ってくると、彼はしたり顔でこう言った。
「衛兵は、女賊刺殺の一件で、すっかり評判を落としたらしいな。なにせ、人だかりにいた誰ひとり、詰め所の衛兵を呼ぼうとせず、直接知らせてきたんだから」
それは、こんな経緯だった。
門衛たちが通常勤務についていると、市民があわてた様子で駆け込んできた。領邸使用人が事故にあった、というのだ。
驚いて現場に赴くと、北門通りの歩道の端に、人だかりができていた。その輪の中心で気絶していたのがオフィーリア。荷馬車に轢かれそうな彼女に気づいて、なんとか助けたまではよかったが、向かいの歩道に転げこんだ拍子に、失神してしまったとのこと。そうした見立てに詳しい者がいたらしく、外傷もなく、伸びているだけだということなので、彼女を領邸まで連れ戻り、正門詰め所で保護していた。
ちなみに、彼女を助けた通行人の話によれば、事故当時、現場の歩道は無人だったという。なぜ、そんな所に、彼女がいたのか分からない、とも。
でも、とオフィーリアは釈然としない思いで眉をひそめる。確かに、突き飛ばされたのだ。無人だなんて、あり得ない。こちらを車道に押しやった後、素早く逃げ去ったに違いないのだ。
北門詰め所が近い場所柄、てっきり衛兵の仕業だと思っていた。昼に会ったジョエルにも、気をつけるよう言われている。だが、衛兵は事故のことさえ知らないという。一体何がどうなっているのだ。それなら一体、
「……誰なのかしら」
あの時、背中を押したのは。
階段の冷たい石板を、月明かりが白々と照らしていた。
時おり風がゆきすぎて、邸内の樹木が黒々とうごめく。
無人の階段でどれくらい、膝をかかえていたのだろう。果てなく広がる夜空をながめ、オフィーリアは目元をぬぐう。
全てがとことん、みじめだった。生涯最悪の日かもしれない。なのに、なぜ、彼を嫌いになれないのだろう。彼でなければ、だめなのだろう。あんなにひどいことを言われたのに。
帰り道、眼鏡をはずして歩いてみた。ぱっとしない器量でも、少しはましになるのではないか、そうすれば世界が変わりはしないか、そんな期待を抱いたのだ。だが、結果はといえば、散々だった。
そう、まったく散々な一日だった。初めて好きになった人に、面と向かって突き放された。馬車に危うく轢かれそうになった。しかも、その上──泣き濡れた顔を、かかえた膝にすりつける。
「……手紙、なくした」
とっさに手を振り払い、彼から逃げたあの時までは、確かに持っていたはずだった。ならば、夢中で駆けていた最中か。なんてドジ。宛名も差出人も書いてあるのに。
今ごろ誰かに拾われて、大笑いされているのだろう。幼い頃のあの時のように。
『こっちくんなよ、ブス!』
幼いあの日、あの子に言われて傷ついた。以来、異性と話すこともできなくなった。そんな勇気が出るはずもなかった。だから、ずっと、男友達の一人もいなかった。
だって、声など、かけられない。みんなみたいに可愛くないから。こんなチンクシャじゃ気後れするから。相手にされるはずなどないから。背伸びをしたって笑われるだけ──。
なのに、きれいな髪のあの人は、普通に笑いかけてくれた。素直でかわいい同僚たちと、わけ隔てなく接してくれた。こんな眼鏡の女でも。
あの人なら、と思ったのだ。彼のためなら、なんでもしようと。彼の役に立てるなら、自分にできることなら、なんでもすると。
自分には、お洒落な皆が持っているような楽しい時間と引き換えに、これまで培った知識がある。"それ"だったら、できるから。できることは、"それ"しかないから。
けれど、きれいな髪のあの人は──
『俺は、女子供は信用しないと決めている』
ちくり、と胸が鋭く痛んで、オフィーリアは唇を噛む。
彼は既に持っているのだ。十分に持っているのだ。要らないものを差し出しても、人は決して喜ばない。
ふと、泣きはらした顔を、オフィーリアはあげた。
白い石段を、怪訝に見あげる。今、頭上で物音がした。
「……奥の部屋で、調べものでもしていたのかしら」
不審に思い、立ちあがる。館内に灯りはなかったはずだ。鍵もしっかりかかっていた。資料館は閉館している。
月下の階段をあがっていくと、果たして、踊り場に人影があった。
人影は扉に向かっていて、鍵をかけているようだ。こんな夜更けに官吏だろうか。資料館を訪れる者は限られる。逆光でしかと見定めることはできないが、大きな帽子をかぶっている。直線的なシルエットは男性のようだ。
「──あの」
おそるおそる声をかけた。ふと、人影が振りかえる。
ばさり、とマントが月の蒼光にひるがえった。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》