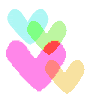
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 12
( 前頁 / TOP / 次頁 )
ぴん、と立った帽子の羽根が、夜風にかすかになびいていた。その広いつばの下、細く編んだ三つ編みが数本、肩の下まで垂れている。
口元にたくわえた上向きのヒゲ。背中を覆う黒い縮れ毛。目元が黒いマスクで覆われているため、口元しかわからない。
白いブラウス、首元のボウタイ。腹には黒のカマーバンド。満月を背負った出で立ちは、古式ゆかしい貴族の正装──むしろ、ずっと時代をさかのぼり、大昔の騎士を彷彿とさせる。むろん、どこからどうみても官吏ではない。
「……どなた、ですか?」
おそるおそるオフィーリアは尋ね、ふと、それを見咎めた。
向こう側の肩の下に、男は何かを携えている。片手で持てる四角く角張った薄い物。──男の腕から垣間見えるのは、見覚えのある金の額縁。──絵画?
あっ、とその正体に気がついた。
「それは 『乙女のまどろみ』 ではありませんの?」
高名な画家 タダ=サイテスが描いた傑作だ。資料館二階の中央の壁にあったはず。
「それを、どこへお持ちになるの?」
問いに男は沈黙し、足を踏みかえ、身じろいだ。「──あ、いや、本日は、この絵の修復に伺ったのだ」
「……修復師の方?」
思わぬ応えに面くらい、オフィーリアはしげしげ相手をながめる。
(芸術家って風変わりよね……)
絵画の修復は芸術の領分。精神性の高い芸術家には、往々にして変わり者が多い。あの時代がかった装束も、つまりは、そうしたこだわりなのだろう。
夜につつまれた邸内に、怪訝に視線をめぐらせる。「でも、こんな夜分に?」
「だからこそ、都合が良いのだ」
は? とオフィーリアはまたたいて、しばし絶句で考えた。「……。そう、確かに、支障はございませんわね。閉館後なら、利用者もおりませんし」
「さて、そろそろ失礼せねば」
男はそそくさ踵をかえす。「では失礼。いささか時間がありませんのでな」
「あの、お尋ねしても、よろしいかしら」
ふと、オフィーリアは顔をあげた。「右手のそれは、なんですの?」
足を止め、男は渋々視線を落とす。指摘の先には、唐草模様の風呂敷づつみ。
「お、おお。いや、これは古来伝統の必須アイテムでしてな。このような獲物──いやっ! 絵画を包んで保護するものです」
しどもど説明、あたふた絵画を包みだす。
なぜかしゃかりきな男の様子を、オフィーリアは「そうなのですか……」とながめやった。
「あの、なぜ室内でお帽子を?」
やっとのことで絵画を包み終わった仮面の男は、なぜかそわそわ目をそらし、そそくさ脇をすり抜ける。「これも欠くことのできない居え物でしてな。では、これにて失(礼)──」
「あの」
「──なんですかなっ!?」
「もしや、御髪(おぐし)の宝石は」
ぴたり、と男が足を止めた。
「かのブラック・ナイトではございませんこと?」
階段を降りかけた肩越しに、仮面の目で一瞥する。
上目使いで小首をかしげ、オフィーリアは記憶をたどった。「確か、ランバート伯爵家が断絶した折、市井に流出したという。以降は行方知れずとか」
「──いかにも」
男が咳払いして振り向いた。「いや、貴女のようなご婦人に、よもや見咎められようとは」
「なんでも、強大な運をもたらす魔石とか」
「ほう。よくご存じですな」
「ですが、これは──」
オフィーリアは言いよどんで視線をそらす。
さよう、と男は心得たようにうなずいた。
「確かに、このブラック・ナイトは強大な運をもたらします。しかし、同時に、持ち主に災いをも呼びこんでしまう」
まあ、とオフィーリアは口元に手を当てた。「恐ろしくはないのですか? そのようなものを」
ふっ、と男は口髭をゆがめた。
「災い結構。それしきの危殆を恐れていては、蒐集家たる者、務まりません。しかし──」
しげしげオフィーリアに向き直る。
「いやはや、おみそれ致しました。そうした事情にまで通じていらっしゃるとは。失礼ながら、由緒ある家柄のご息女とお見受けするが」
「申し遅れまして。わたくしは──」
スカートをつまんで礼をとり、オフィーリアは身分を名乗った。ラトキエゆかりのパルム男爵家の一人娘。つまりは家の跡とり娘。ちなみに、この領邸勤務は社会勉強、行儀作法見習い中の身の上である。
三つ編みの先のブラック・ナイトに目を向ける。
「以前、書斎の図鑑で見ましたの。闇の中で華やかな表情をみせる、美しく希少な宝石ですわ。でも、実物を見るのは初めてで──あの、拝見してもよろしいかしら」
片足を引き、男は胸に手を当てた。
「可憐な乙女に求められるなら、我がブラック・ナイトも喜びましょう」
貴族が行なう正式な礼だ。片腕でマントをひるがえし、仮面の紳士は進み出る。
「ブラック・ナイトは個体差が激しく、入手が大変難しい。この遊色は、直線の帯状で現れます。動かせば、このように、手の動きに付いてきます。光の分散度がきわめて高く、キラキラと輝いて、この華やかな美しさを──」
一しきり講釈を垂れると、男は感心したように目をあげた。
「しかし、貴女が初めてです。この価値を正しく評したのは」
三つ編みの先から別の煌めきをとり外し、男は目線で促した。
「よろしいかな? お手を」
戸惑いつつもオフィーリアは、言われるがままに手を差し出す。そのひらいた手の平に、男は白手袋をはめた手で、うやうやしくそれを置いた。
「貴女にも、一条の僥倖を」
闇の中、豊かにきらめく緑のゆらめき。
……橄欖石(かんらんせき)? とオフィーリアは顔をあげる。
「"フェアリー・ブライト" 貴女に幸運をはこびます」
いつ、いかなる時にも、あなたが幸せであるように。
ひらり、と男がマントの裾をひるがえした。
「では、私はこれにて」
するりと脇をすり抜けて、素早く階段を降りていく。
姿は、すぐに闇にまぎれた。
木立の暗がりに消え入った後ろ姿を見送って、オフィーリアは手の平のきらめきに目を戻した。
小指の爪ほどの小さな石が、暗がりの中で輝いている。幸運をはこぶ"フェアリー・ブライト"
「……でも、今頃こんな物をもらっても」
この皮肉に、嘆息する。夢破れたばかりというのに。
風変わりな紳士が立ち去って、辺りが急に、しんとする。
闇が一段と深まっていた。空には星々が瞬いている。澄んだ夜につつまれていると、昼の記憶がよみがえった。
ぱたん……ぱたん……と力を抜いて、オフィーリアは石の階段をおりる。
憂鬱な気分で寮に戻り、月明かりの階段をわずかに軋ませながら二階にあがり、灯りの絞られた廊下を歩いた。同僚たちは各自部屋に引きあげたようで、誰の姿も既にない。消灯していた玄関ホールを抜けた時、壁の暗がりの文字盤は、九時過ぎをさしていた。濃紺の空の高みで、丸い月が輝いている。
薄闇の廊下をひとり自室に向かいつつ、オフィーリアは嘆息する。母から手紙が届いていた。縁談が舞いこんだのだ。
ついに、来たるべきものが来た、胃の腑の底に重石が落ちるような衝撃とともに、抱いた想いがそれだった。そして、苦い諦めが広がった。
末端とはいえ貴族の系譜。その娘として生まれた以上、決められた相手との婚姻は、果たさねばならない義務だった。この身の夫となる者は、少しでも財産の多い、縁故とするに有利な家柄。一族を盛り立てる手腕と才覚を具えた者。風貌や年齢、人柄などは考慮すべき要素ではない。それは当たり前のこととして育ったし、理解もしているつもりだった。この婚姻には一族の命運がかかっている。この肩に、一門の盛衰がかかっている。それは十分わかっている。けれど、その前に、一度でいい。
自力で恋がしたかった。流行りの服で着飾って、すてきな恋人と街を歩き、おしゃれな店でお茶を飲み、日が暮れるまでお喋りをして。みんなが、楽しんで、しているように。
けれど、この現実は、あの彼のまわりには、かわいい娘たちが大勢いて──
オフィーリアは顔をゆがめ、きつく唇を噛みしめる。
「……かないっこない」
わたしなんか、かないっこない。
涙があふれ、ぼろぼろ頬を伝っていく。彼はもう知っているだろうか。あの後、親衛隊ができたのを。冷たい目をしたあの人は。
暗い廊下に立ち尽くし、うつむき、両手で目元をぬぐう。
そんなに多くは望まない。恋人でなくても構わない。そんな分不相応は望まない。自分の器量はわかっているから。そばにいられれば、それだけで、彼の役に立てるだけでいいのに。それで、彼が笑ってくれたら。けれど──
──もうだめ。あの人を本気で怒らせた。
胸の痛みに耐えかねて、かたく、かたく瞼をつぶる。
それにもう、時間がない。母に返事を書かねばならない。承知した旨書き送り、家に戻って結婚に備え、屋敷の女主人となるべく修練を積み、跡継ぎを産むべく力を尽くし、自由な娘時代に別れを告げて──
夢は、やっぱり叶わなかった。
泣き濡れた頬で、熱く深い吐息をつき、二人部屋の扉を押しあける。
室内に、灯りはない。同室の同僚は、ミモザ祭で休暇中、泣きはらした顔で戻っても、詮索されることがないのが救いだ。こんなに泣いたのは久しぶり。泣き続けて頭が痛い。人生、本当に負けっぱなしだ……
ぐい、と片手で頬をぬぐい、灯りをつけようと手を伸ばし、ふと、オフィーリアは振りかえる。
窓からの月明かりで、板床に窓枠の影が落ちていた。
向かいの窓はあいたまま、夜気がゆるく吹きこんでいる。左の壁の机と寝台。暗がりに沈んだ壁掛け時計。返事を書きあぐねたペンの下、置きっぱなしの便箋が白い。
ひっそりと暗い、いつもの部屋だ。何も変わったところはない。──いや、右壁の暗がり、本棚の向こうに誰かいる。
「こんばんは」
夜陰にまぎれて腕をくみ、壁にもたれた男が言った。
男はおもむろに背を起こし、月明かりに顔がさらされる。長めの髪が振りかかる、引きしまった頬の線──
オフィーリアは息を呑んだ。
「……ザイ、さん」
ずっと、ずっと、考え続けた、当の彼がそこにいた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》