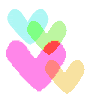
■番外編 「メガネちゃん狂想曲」 13
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「……どう、して」
オフィーリアはまごつき、目をそらした。ザイはゆるりと腕組みをとく。
「よしてくれませんかね、ああいう真似は」
カツン、と板床に踵を鳴らして、潜んだ壁から歩みでる。
「正直言って、迷惑ですよ」
色素の薄い髪と顔が、暗がりで白く浮き立っている。
彼にしては珍しく、シャツとズボンだけの軽装だ。もっとも、ぴたりと肌に沿う黒の上下は、闇に溶け入り、なじんでしまう。何かを応えるより早く、「早速ですが」と向き直った。
「殴っていいスよ、俺のツラ」
オフィーリアは目をみはった。「──ど、どうして、そんな」
「あんたには、そうするだけの理由がある」
戸惑い、目を泳がせる。
口調を押さえているものの、にこりともしない真顔から、静かな怒りが伝わってくる。ふざけて後ろから声をかけた、昼の出来事が脳裏をよぎった。ゆっくり肩越しに振り向いた横顔。冷ややかな視線。辛辣な口振り。まだ、彼は怒っている。
ザイは投げやりに手を広げる。「どうぞ。遠慮は要りませんよ」
「で、できません!」
オフィーリアは首を振って後ずさった。小首をかしげて、ザイは見返す。「いいんスか? 殴んないで──じゃ」
右の肩を、無造作に引いた。
「なら、こっちの用向きを片付けさせてもらいますかね」
向こう側に隠れた利き手は、腰の辺りを探っている。
床に視線を落としたままで、オフィーリアはおどおど口をひらいた。「だ、だって、わたし、そんなこと──そんなこと、しなくていいです。でも、その代わり──」
軽くかがんだ体勢で、ふと、ザイが動きを止める。
「教えて欲しいことがあります。今日、昼間、ザイさんは──」
「俺と取引しようってんですか?」
オフィーリアは目をみはった。「と、取引だなんて、そんなつもりは」
「交換条件ってことでしょ、つまりは」
そっけなく言われ、返事に詰まる。
言葉をなくして当惑し、だが、口を引き結んで、うなずいた。「……はい」
「──へえ。驚いたね」
邪険な声音に、辺りの空気が凍りついた。
ザイはゆっくり肩を起こす。闇に沈んだ腕の先、節くれ立った指が白い。
オフィーリアは動揺した。二人の間に壁ができ、一瞬にして隔たった気がした。初めのうち彼はまだ、腹を立てていただけだった。だが、今はそれだけではない。なにか穏やかならぬもの、不審のようなものが紛れている。
わずかに苛立った佇まいで、ザイはゆっくり顎をなでた。「あんたみたいな素人に、ねじ込まれるとは思いませんでしたよ。ずいぶん俺もなめられたもんだ。話をすり替えようたァね」
皮肉を含んだ苦笑い。オフィーリアはあわてた。「す、すり替えるだなんて! そんなつもりはっ!」
「そいつを拒めば、どうします?」
そっけなく切り返されて、オフィーリアは返事に詰まった。おどおど胸で両手を握る。「だって、ザイさんのことを叩くなんて、そんなこと、わたしにできるはずが」
「あんたにツラを張られたところで、どれほどのことでもありませんよ。好きなように叩けばいい」
「──でも」
「先に言っておきますが、俺がここに来たことは、あんたにとっては災難ですよ」
「で、できません」
「なら」
ザイは投げやりに手を広げた。「今の話はナシってことで」
むっ、とオフィーリアは見返した。
「そ、そういうやり方は卑怯です」
「──卑怯? あんたが自分で降りたんでしょうが」
「だって、今のは横暴です。一方的に取り下げるなんて」
膝の震えを叱咤して、それでもオフィーリアは相手を見据える。
「あなたは今、わたしには、理由がある、と言いました。話をもちかけたのは、あなたです」
さわり、と夜風が吹きこんで、窓辺で白くカーテンが舞った。
ひっそり闇に沈んだ部屋に、どこからか遠く、人の声が聞こえている。ザイは思案するように目をすがめた。
「──上手いじゃねえスか」
ふっと軽く口元をゆがめ、腕をくんで壁にもたれる。
「俺に訊きたいことってのは?」
存外に静かな口調だ。
びくついていたオフィーリアは、肩にこもった力を抜く。怖気づく己を叱咤して、顎をあげて目を据えた。
「昼間、あなたは言ったでしょう? "女子供は信用しない"って。でも、どうして、そんなふうに」
ザイは虚をつかれたような顔をした。
「──それが、訊きたいことですか?」
拍子抜けしたようにそう尋ね、戸惑い顔で口元をつかむ。「一体何を言うかと思えば──そんなことでいいんスか?」
「教えてください。わたしには大事なことなんです!」
凝視し、オフィーリアは言い募った。
昼間、彼と話した折りに、その一言で一蹴された。彼はそつなく接していても、その一線を越えた先には、決して他人を立ち入らせない。今も「そんなこと」とは言うものの、表情は明らかに苦々しげだ。
今の反応で確信していた。この壁を突破できねば、いつまでたっても門前払い。のらりくらりとあしらわれ、彼の核には辿りつけない。
ザイは軽く舌打ちし、忌々しさをわずかに含んだ、押さえた声音で目をそらした。「聞いたところで面白くもねえ、ろくでもねえ話ですよ」
口調に棘が入り混じり、見覚えのある獰猛さが、刹那、顔を覗かせる。
オフィーリアはたじろいだ。昼の失態が頭をよぎり、足裏が浮くような怖気が走る。だが、唇を引き結び、相手が口を開くのを待った。ここで引いては元の木阿弥、振り絞った勇気が無駄になる。
目を凝らすような横顔で、ザイは闇の中、沈黙している。
やがて、ゆっくり身じろいで、観念したように息をついた。
「知っての通り、隣国は、始終、戦に明け暮れていましてね。大陸の東の寄せ集めが、西の帝国に盾突いて、東西の境モンデスワールを盟主とする同盟を組んで抵抗している。片や、西の帝国は、東の辺境の寄せ集めを躍起になって叩いている。それで、こっちの仕事ってのが、東の偉いさんに頼まれて用心棒なんかをするんですが、俺らの職場は──まあ、ちょっと荒い現場でね」
思いがけない落ち着いた声に、オフィーリアは密かに安堵した。とはいえ、なにか、奥歯にものの挟まったような物言いだ。
「俺はあの頃、相棒の親友とつるんでて、奴と現場を渡り歩いていた。で、ある晩、痩せた女を拾いましてね。何日もろくに食ってねえってんで、なんの気なしに連れ戻ったんですが──。今にして思えば迂闊だった。恨みを買う商売なんで注意を払ってはいたんですが、あの時は、うっかり、ほだされちまって」
苦い物でも飲み下すように、ザイは投げやりに嘆息した。
「次の朝、女は消えていて、こっちは取り返しのつかねえことになっていた。素性の知れねえあんな女を、連れ戻ったばっかりに」
オフィーリアは顔をしかめた。
「あの、お金を盗られたとか?」
いや、とザイは苦笑いで首を振る。「金で済めば、良かったんですがね」
口の重い向かいの様子を、オフィーリアは恐る恐るうかがう。「もしや、お怪我をなさったの?」
ふっとザイは小さく微笑った。
「──まあ、そんなところ、でしょうかね」
返事に窮し、オフィーリアはやきもき考えた。どうやら、連れ戻った女性が原因で、友人が怪我をしたらしい。それを、彼は気に病んでいる。けれど──
「あの、悪気があってのことではないなら、お友だちも怒ってはいないんじゃないかしら」
「さあ。そいつとはもう、会ってねえんで」
ぶっきらぼうにザイは言い捨て、さばさば話を切りあげた。
「まあ、そういうわけなんで、か弱そうな素振りで近づく奴は、信用しないと決めたんですよ」
「……わたしもですか?」
オフィーリアは眉をしかめた。
「その中に、わたしも入っていますか? でも、だからといって一切合財、切り捨ててしまうおつもりですか」
ザイは怯んだように口をつぐんだ。
ばつが悪そうに目をそらす。「──こういう所にいる人には、言ってもわかりはしないでしょうが、俺らがいる場所ってのは、こことはまるで違うんで。そうするのが自分を守るためであり、周りの奴らに迷惑をかけないためでもある」
「信用できませんか、わたしのことも」
ずい、とオフィーリアは身を乗り出す。ザイは困ったように苦笑いした。「──食い下がりますねえ、珍しく」
「茶化さないで! わたしはお金を盗ったりしないし、あなたに怪我をさせたりしないわ!」
ザイは口をひらきかけ、だが、眉をひそめて口をつぐんだ。
窓辺で、カーテンがゆれていた。
灯りのない部屋の中、机に広げた物たちが、ひっそり暗がりに沈んでいる。ぼんやりと白い封筒と便箋、書きかけの手紙、転がしたペン。月明かりの射しこむ床に、窓枠の濃い影が落ちている。
ザイが身じろぎ、息をついた。「……よく似合っていますよ、赤が」
返事を待っていたオフィーリアは、肩透かしを食い、瞬いた。
「眼鏡ですよ。あんたによく似合ってる」
言葉に詰まり、首をかしげる。「あ、あのっ?……でも、昼間はザイさん、わたしのことを──」
「ちょっと、うまくねえ問題がありましてね」
ザイは捨て鉢に頭を掻いた。「それで、つい当たっちまって」
途方に暮れたような横顔に、オフィーリアはたじろいだ。何か雰囲気が変わった気がする。気のせいだろうか。態度を軟化させたように思うのは──はた、とそれに思い当たった。
「もしかして、セレスタンさんですか?」
ザイが怪訝そうな顔をする。
「あの人が何か、ザイさんに──その、ぶったり、とか」
ザイは思案を巡らして「……ああ、そういう話でしたか」と顎をなでた。
「いえ、奴は、別に何も。まあ、手ぶらで来るのもなんなんで、なんかねえかと思ったんですが、適当な土産が思いつきませんで」
「おみやげ、ですか?」
話の飛躍に面くらい、オフィーリアは目を瞬く。「どうして、わたしにお土産を?」
「だから」
ザイはじれったそうに嘆息した。
「だからこうして、詫び入れに来てんでしょ?」
ぽかん、とオフィーリアは自分をさした。
「……もしかして、謝りにいらしたんですか?」
「そう言ってんでしょ。さっきから」
唖然とオフィーリアは突っ立った。「……でも、あの、わたしのことを怒っていたんじゃ?」
「怒ってますよ。当たり前でしょ」
ぶっきらぼうにザイは言い、息を吐いて腕を組んだ。「ろくに見えもしねえのに、車道を突っ切ろうってんだから」
「……え?」
「よしてくれませんかね、ああいう真似は」
ぽかん、とオフィーリアは瞬いた。予想外の返答だ。
とりあえず「……は、はあ。すみません」と小さくなってうなだれる。北門通りのあの事故を、彼はもう知っているらしい。
「命を粗末にするもんじゃありませんよ。あれしきのことで、馬車に飛びこんでやろうとか」
「は? いえっ! 違うんです、あれは!」
あわててオフィーリアは首を振った。「あれは、そういうことではなくて、ちょっと、その、練習を」
「練習?」
いぶかしげに問い返され、しどもどしながら、うつむいた。「あの、眼鏡がなければ、少しはましに見えるんじゃないかって。だから──」
「なに考えてんだ!」
びくり、とオフィーリアは首をすくめた。
ザイは苦りきった顔で嘆息する。「たく。利口なんだか馬鹿なんだか! ちょっと無茶が過ぎますよ」
「──だって!」
むっ、とオフィーリアは顔をあげた。
「だって、あなたが言ったんじゃない! 賢しい女は嫌いだって!」
「眼鏡が気に食わねえなんて、俺は一言も言ってませんよ」
「でも! あんな言われ方したら誰だって! だって、わたしはあなたのことを──」
はっと、オフィーリアは口をつぐむ。ザイが静かに見返した。
「惚れた女がいましてね」
鋭くオフィーリアは息を呑み、あわてて床に目をそらした。
顔をゆがめて唇を噛む。「……やっぱり、みんなみたいに、かわいくないから」
「あんた、鏡を見たことありますか?」
「──どうして、そんなひどいこと言うの? わかっています。不細工だってことは」
ザイが怪訝そうに身じろいだ。
「幼なじみの男の子からも、散々ブスだって言われたし」
床の一点を見やった耳に「……あんたねえ」と呆れたような溜息が届く。
「不細工に向かって面と向かってそう言える奴は、滅多なことじゃいねえでしょうよ」
怪訝にあげた視界の先で、ザイは身じろぎ、向き直る。
「かわいい顔、してますよ。あのメイドさんたちにも負けねえくらいに」
だから、あのハゲだって、血相変えて来たんでしょうに、と放り投げるように独りごちる。オフィーリアは力なく首を振った。「……いいんです。慰めてくれなくても」
「あんたをもちあげる義理はありませんよ」
面倒そうにザイは言い、しげしげと眺めやった。「あんた、その幼馴染みとやらに、惚れられてたんじゃないんスか?」
唖然と、オフィーリアは絶句した。「──まさか、そんな」
「男のガキなんてのは、しょうもないもんで、一度はやらかすもんですよ。好きな相手をわざと苛めてみたりとか」
二の句が継げずに困惑し、わたわた視線を泳がせる。「そっ、そんなはずはありませんわ。だって、わたし、男の方から、そんなふうに言われたことは、今まで一度も」
「そりゃ、大抵の奴は引くでしょうよ。あんな珍妙な眼鏡をかけていりゃ。言っちゃ悪いが、ひでえセンスだ」
「ちっ、違います! あれは──」
オフィーリアは目をみはって首を振った。「あれは、わたしが選んだものでは──あの、母がくれたお祝いの品で、だから、使わないわけには──」
あー、母ちゃんの陰謀か、とザイはぼそりと横を向く。
ついていけないオフィーリアは(……いんぼう?)の顔で固まっている。
「まあ、理由はどうあれ」
ザイはゆるりと腕を組んだ。
「あんたには、可哀相なことをしたと思いますよ」
息を呑み、オフィーリアはうつむいた。
わななく唇を噛みしめる。ザイが怪訝そうに声をかけた。
「──なんで泣いてんです?」
ためらい顔で、途方に暮れたように頭を掻く。「──だから言ったでしょうに。俺が来たことは災難だって」
「……ザイさん」
「はい?」
「待っていてください」
オフィーリアは顔をあげた。涙をぬぐい、断固たる顔で相手を見据える。
「ここで、少し待っていてください。お時間はとらせませんから」
ザイは気圧されたように口をつぐんだ。「──そりゃまあ、俺は別に構いませんが」
オフィーリアはうなずき返し、人けない廊下へ飛び出した。
腕を振り、月明かりの廊下を、がむしゃらに走る。
──あの人が好き。
あの人が好き! あの人が好き! あの人が好き!
暗い廊下が涙で曇った。
今、「できること」があるはずだった。彼のために「できること」それを知っているはずだった。
本当は、ずっと気づいていた。
北門通りで親子の事件があった後、通りを一緒に歩いた時から。彼が何かと見ている相手に。彼がいつも話しかける相手に。
寮の廊下を一心に走る。
心に決めたはずだった。彼の役に立てるなら、彼のためなら、
──なんでもすると。
はあはあ息を切らして足を止め、ぐい、と腕で涙をぬぐう。
見慣れた扉を押しあけた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》