( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
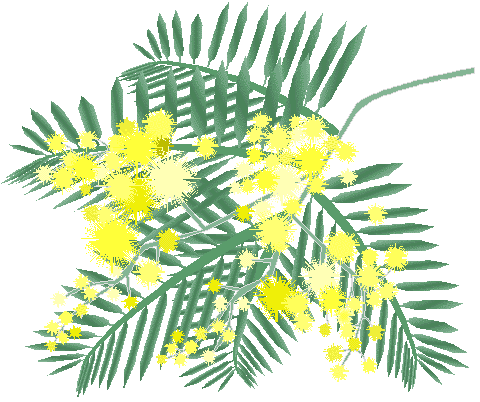
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 10話5
( 前頁 / TOP / 次頁 )
あぐらに置いたその手を伸ばして、セレスタンは茎を取りあげた。
つまんだ二指をすり合わせれば、柔らかな華やぎを振りまいて、明るい黄色がくるくる回る。
『なら、お前には、俺からやろう』
誰かが持ってきた見舞いなのか、首長は別のミモザを持っていた。
『知ってんだろ、"幸せのおすそ分け" カレリアでは、今日はそういう日らしいからな』
そして、いささか呆れた顔で、のたまった。
『あのなあ、お前、考えてもみろよ。粛清された頭領の手下が、どれだけいると思ってんだ。むしろ、恨みつらみをかかえた輩が、ロムってのは大半だぜ。あの頭目たちの島はでかかったからな。そもそもロムは、その手の奴らで再編した組織だぞ? そういう素地が発覚する都度、いちいち取り合って切ってたら、組織自体が立ち行かねえよ』
他人のことになんか構うなよ。
お前は自由に生きてきゃいいんだ。お前の時間は、お前が好きに使えばいい。
考えがある、と首長は言った。
そして、ひらひら手を振って、テントの外へ出て行った。
『実際問題、お前に抜けられると痛いからな。ザイと張れるのはお前しかいねえし、アドんとこには負けたかねえんだよ』
「……やっぱ、最後のあれが本音だよな」
つまんだミモザをくるくる回し、首長から贈られた件の言葉を、唇の端にのせてみる。"幸せのおすそ分け"──つまり、この国の祝祭に乗じて見逃した、ということだった。
あからさまな殺意と裏切りを。
溜息まじりに花をほうって、防水シートに後ろ手をついた。
禿頭の首を背に倒し、セレスタンはげんなり天を仰ぐ。「たく、なんていい加減なジジイなんだ。珍しく真面目に語っていたから、こっちも真面目に拝聴すれば。あんなちゃらんぽらんな親父は見たことねえよ。でも、まあ、あれで頭(かしら)は頭(かしら)だし、ザイに苛められたら、助けてやんなきゃなんねえし」
天井の布地を、影がよぎった。上空を滑空する鳥だろうか。
「……実際、俺は忙しいんだよな、死んでる暇なんかねえくらい……姫さん泣いたら慰めてやらなきゃならねえし、副長が暴走したら体張って阻まにゃならんし、隊長がまた奈落に落ちたら──」
ふっつり、ぼやきの口を閉じた。
白く明るい天井を、目を細めてながめやり、よっ、と背中を引き起こす。
「引っ張り戻さにゃならねえし」
前かがみのあぐらの膝に、左右の肘をゆっくりと置いた。
「──ねえ、おやっさん」
柔らかく語りかけた視線の先には、小指から引き抜いたリングがあった。
年季の入ったアーマーリング。その銀の金属が、鈍く光を弾いている。
「俺は、どうしたら、いいんすかねえ。隊長を狙って、ずっと近くで注視てきたから、あの人のことは誰よりよく知ってるんすよ。ガキのウォードを始末できずに、部隊に連れてきちまったこと。代理に処分をせっつかれ、一人でずっと苦しんでいること。未だに妊婦の夢を見て、夜になるとうなされること。羊飼いを殺られて動揺し、無茶な南下を指示したこと。姫さんのことが心配で、心配で心配でしょうがなくて、大事な隊をほっぽり出して、でたらめにつっ走ってきちまったこと。冷酷無比な戦神どころか、あれほど人間臭い人はいない。──わかってんすよ本当は。隊長がおやっさん達を殺ったのは、女をなぶり殺した報復だって」
身寄りのない妊婦の仇を、あのヴォルガで討ったのだと。
生きたまま腹を割かれた彼女と同じ目にあわせることで。
ケネルの非情を知らしめたヴォルガは、未だに非難含みで語られるが、当人は何も弁明しない。
「隊長を殺ろうと近づいたあの時、俺は敵の接近に気づかなかった。それを、副長が割りこんで助けてくれた。でも、あんな無茶するもんだから、自分が腕やられちまって」
もっとも、あの時、彼が引き戻していなければ、その場で串刺しになっていた。
硬いリングをそっとなで、「ねえ、おやっさん」と語りかける。
「縄を切って逃げた時、ザイの足なら追いつけたんすよ。なのに、奴はこなかった。レオンも足を射抜かなかった。ロジェは縄をゆるく打ち、ダナンは薬を軽く盛り、ジョエルは火薬を加減した。みんな、俺の仲間なんすよ。俺は"ここ"にいたいんすよ。実際連中が消えちまえば、毎日が退屈で死にたくなる。本当にそれでいいんなら、頭の言うことが本当なら──」
ぐにゃり、とリングが指先でひしゃげた。
「捨てちまっていいすかね、俺の業」
潰した形見を見つめる頬を、苦笑の形にセレスタンはゆがめて、うつ伏せの彼女を一瞥した。「──そりゃ、わけないすよ。こんな細っこい首ひねるのなんざ」
今にして思えば、あの時点で、わかっていたことだった。それが自分にはできないことは。彼女を仕留め損なった、三階の廊下の、今朝の時点で。
上着の隠しに手を突っ込み、セレスタンは形見を押し込んだ。
「だって俺は、生きていかなきゃなんねえから」
いつもの黒眼鏡を、取り出し、かける。それを自らに言い聞かせ、セレスタンはゆっくり後ろ手をついた。
「……まったく、いい天気だねえ」
首を倒してながめると、布張りの天井は昼の光に満ちていた。時おり影がよぎるのは、上空を走る雲だろうか。
暗いわだかまりは放逐されて、世界は白々と明るかった。小石転がる地面の上に、光が柔らかく射している。妄執の終焉にふさわしい、ぽっかりと空虚な、始まりの場所。
世界は、びくともしなかった。
天地が覆ってしまうような一大事変があったというのに、何も変わりはしなかった。かたくなに、秘密裏に守ってきた、ひとつの世界が壊れても。
それは友好的な色彩に満ちて、依然として目の前にある。どれほどいびつな裏切りも時のうねりに呑みこんで、ただ茫洋とひらけている。どれほど悲痛で切実な叫びも、どれほど壮絶な諦念も、世界は何も拾いあげず、また、何も与えはしない。ただ、あるがままに、そこに在る。
彼女の枕元でまどろむ雛が、羽毛を揺すって身じろいだ。あの小さな生命の営みも、また──
そう、あの時、幕引きをためらわせたのは──青鳥の雛に見たものは、あるいは"可能性" だったかもしれない。捨て去るには惜しくなった、抗いがたいきらめきは。
「月日はめぐり、世界は変わる……」
その言葉を、そっと唇にのせてみた。
かの首長から贈られた、それは"幸せのおすそ分け"
それは、彼女に突っ返したはずのものだった。なのに、たちまち別方向から、またも投げつけられてしまった。皆が皆に手渡して、いつの間にやら手の中にある。それではもはや
"おすそ分け"というよりは "幸せ"の押し付け合い──。
彼女と首長と自らが、三角形になって、ぐるぐる回る、奇妙な構図を想像し、ふっとセレスタンは頬をゆるめた。
「……おせっかいな奴が、世の中には多いな」
苦笑いした黒眼鏡の下を、雫が一すじ、伝って落ちた。
それからしばらくたった頃、とある噂がバパ隊の中に広まった。
セレスタンがかの賓客に駆け落ちを迫り、みごと玉砕、ふられたらしい、と。
それを聞いた隊員たちは面白半分ではやし立てたが、真相を訊かれた特務の彼らは、ただ微笑ってあしらうばかりで、本当のところはわからなかったという。
彼ら特務の班員に、異を唱える者はいなかった。あの後、首長が語って聞かせた顛末に。
それは、およそ、こんな話だ。
西の森での捕り物の末、樹幹から脱走したセレスタンは、その足で首長の元に出頭した。
そして、申し開きをおこなった結果、彼の冤罪が確定した。
SIDE STORY 「とある夏の昼下がり」
( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
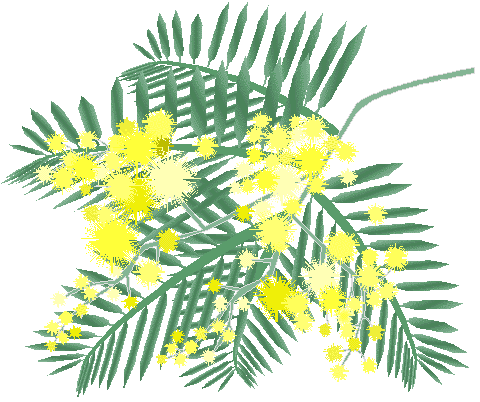
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》