( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
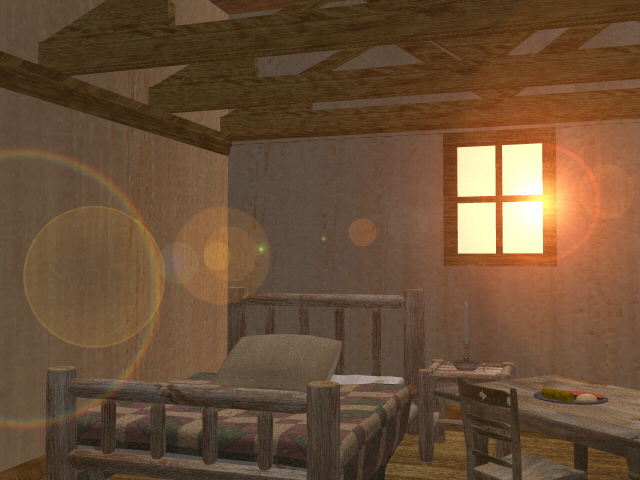
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 10話11
( 前頁 / TOP / 次頁 )
アドルファスの部下が、彼をここへ寄越したのだろうか。首長の心情を慮り、彼女との最後の別れをさせるために。そうでなければ、あのザイか。
他にそんなことが可能なのは、あの男をおいてはない。珍しく気を利かせ、他隊の統率まで引き受けたとすれば──。今日のザイはいつになく、いやに感傷的だった。だが、それなら実に安直だ。彼が医師と鉢合わせになれば、何が起こるか知れていように。いや、ザイは決して鈍くはない。むしろ先の先を読む合理的な思考の持ち主だ。だからこそ、そう踏んだ。
調達屋は、どうせ来ない、と。
それはザイに限った話ではなかった。調達屋の矜持の高さは、誰もが承知していたが、無謀な宣言をした彼が、よもや坑道に現れようとは、あの場にいた誰ひとり、予想だにしなかったに違いない。
いずれにせよ、この事態は最悪だった。
案の定アドルファスは錯乱し、彼女をかかえこんでしまっている。凶暴な気をまき散らし、誰にも彼女を奪われまいと、息を荒げて牽制している。
彼女を掻き抱いた蓬髪の肩に、ケネルは溜息まじりに手をかけた。
「アドルファス、手を放せ。それは、あんたの娘じゃない」
「やめてくれ! もう、やめてくれ!」
アドルファスは激しく振り払った。
うずくまった蓬髪から、くぐもった涙声が聞こえてくる。「……嫌なんだよ。もう痛い思いをさせるのは」
「──アドルファス」
「そんな思いをさせるくれえなら、いっそ、この腕で死なせてやりてえ……」
ケネルは苛立ちをなんとか飲み込む。「──アドルファス、頼むから。それは、あんたの娘じゃないんだ」
「違う!」
野太い声で即座にはねのけ、アドルファスは更に、懐深くかかえこむ。
「俺の娘だ! 俺の娘なんだ! もう、誰にも好きにはさせねえ! もう、他人の好きにはさせねえ!」
黒い蓬髪を振りあげざま、暗がりに銀光が一閃した。
「出て行け!」
すらり、と刃を抜き放ち、アドルファスが不穏にねめつけていた。
「──アドルファス、よせ」
「うるせえ! お前ら全員、外に出ろ! もう、誰にも触らせねえ!」
血走った双眸を怒らせて、蓬髪を振り乱して、吼え猛る。
皮肉なほどの間の悪さに、ケネルは密かに舌打ちした。普段であれば、力づくで引き離すのもやぶさかではなかったが、いかんせん今は、体力がない。まして、この猛者を押しとどめるほどの力が、今のケネルに残っていようはずがなかった。意識を失わないのが不思議なほどに疲労困憊、衰弱している。膝がわらい、立っているのもやっと、という惨たんたる有り様なのだ。
じりじりしながら、ケネルは辛抱強く言葉を連ねる。「──アドルファス。頼む。時間がないんだ」
「俺の娘だ! この俺の娘だ! 誰の指図も、もう受けねえ!」
「つべこべぬかしてんじゃねえぞコラ」
不愉快そうな舌打ちに、ふと、ケネルは口をつぐむ。
「俺様が苦労して連れてきた医者に、なんぞ文句でもあんのかコラ!」
腹立たしげな一喝が、洞窟の天井に反響した。
「──情けねえなあ、まったくよぉ」
眉をひそめた真面目な顔で、調達屋がアドルファスを見据えていた。細い三つ編みをじゃらじゃら振って、嘆かわしげに首を振る。
「なんてザマだよ、砕王の旦那。この首賭けて、俺は医者を調達してきた。それをあんたは反故にする気か」
大きく息を吐き出して、背後の暗がりを指でさす。
「目ぇ覚まして、とくと見やがれ。あの野郎しか、いねえんだよ、客を助けられるのは。そういう理屈がわからねえ、あんたじゃなかったはずだろう!」
額で髪を分けた白皙の男が、薄闇に紛れてたたずんでいた。坑道に駆けこんだ一行を、後から追ってきたらしい。
調達屋は呆れた口調で目を戻す。
「いいのかよ、死んじまっても。あんたは又そうやって、てめえで娘を死なせる気かよ」
びくり、と蓬髪が強ばった。
「あんたの娘、渡してやんな。今ならまだ、間に合うぜ」
無精ひげをわななかせ、アドルファスは食い入るように調達屋を仰ぐ。「……今なら」
「おうよ、間に合う。そこんところは間違いねえ。なにせ俺様が連れてきた、とびっきりの医者なんだからよ。街の看板倒れとは格が違うぜ」
調達屋は大きくうなずき、暗がりでたたずむ件の医師に一瞥をくれた。
「だろ? 先生様よ」
闇医師は身じろいで、持て余したように嘆息する。
がくり、とアドルファスが膝をついた。
彼女をかかえこんだ太い腕から、ゆるゆる力が抜け落ちる。座りこんだ膝に、寝袋をおろした。
「……頼む」
喉の奥から、やっとのことで、しぼり出した声。
ぐしゃぐしゃに泣き濡れた顔を、正座の膝にこすりつけた。
「頼む! 助けてやってくれ! この通り──この通りだ!」
闇医師は無言で見おろして、おもむろに足を踏み出した。寝袋の彼女を眺め下ろして、調達屋を振りかえる。
「話はついたのか?」
おうよ、もう支障はねえ、と調達屋も向き直る。
「ならば、仕事に取りかかるとするか。他の者には出てもらおう」
「ちょっと待てや。まだ話は済んじゃいねえぞ」
外に出るよう手を振った闇医師の言葉をさえぎって、調達屋は真っ向から目をむける。
「この通り、患者はあんたにくれてやる。だが、預ける代わりに条件がある。てめえも医者と呼ばれるからには、てめえの務めはきっちり果たせ。医者の看板掲げる以上は、てめえの患者は必ず助けろ」
おもむろに腹で腕を組み、ぎろりと闇医師をねめつけた。
「それが本職の誇りってもんだ」
誰もいないのに、飛び出してくる。
藪から。幹から。岩場の陰から。
光が一閃するように。風そのものであるかのように。
振り向く間もなく斬られている。
確かに、そこにいるはずなのに、どうしても、居場所を捉えられない。辛くも残る残像は、刃の銀と、獲物を狙う獣の瞳。
底光りする褐色の双眸。
ふってわいた刺客には、表情らしきものはない。これだけの殺戮を仕出かしながら、殺気もなければ、残忍でさえない。愉悦も、殺気も、興奮もない。
誰も彼も、ただの一振りで倒されていく。
アレには感情が欠落している。アレは既にヒトではない。ヒトというより野生の獣、いや、最も正確な比喩は、
──化け物だ。
息を呑んで、跳ね起きた。
「ゆ、夢か……」
シーツを強く握りしめた手が、硬く強ばり、汗ばんでいる。
額を伝う汗をぬぐって、ジャイルズは深く息をついた。
息が小刻みに震えている。今、悲鳴をあげたかもしれない。じめつく生地を指でつまんで、忌々しげに顔をしかめた。下着の綿のランニングが、ぐっしょり汗にまみれている。寝台の上に投げ出した膝が、まだ、がたがた震えている。
それを見やって舌打ちし、ジャイルズは安宿の窓を見た。
昼の鈍い日ざしが射していた。路地裏を行く呑気な声。いつもと変わらぬ穏やかな日常。ここは、もう、安全な場所だ。
ぎしり、と背もたれにもたれかかり、手すりに置いた煙草の箱を、忌々しい思いで引ったくった。朝日に目をすがめたその頬が、笑みの形に不敵にゆがむ。
ここまでくれば、安心だ。
あの獰猛な野獣のことは、既に詰め所に通報した。遠からず衛兵が捕えるだろう。そうだ、あんな化け物を放置すれば、全てを食らい尽くしてしまう。
あれを野放しにするのは危険だ。ザンバラ髪の遊民が「ウォード」と呼んだ若造を。
「よう、ずいぶん魘されていたな」
ぎょっと声に振りかえると、開け放った戸口にもたれて、男がにやけた顔で眺めていた。
ぶらぶら足を踏みこんで、男は馴れ馴れしく肩を抱く。
「助かって良かったじゃねえかよ。あの化け物に睨まれて、助かる奴なんぞ、そうはいねえぞ? ま、誰のお陰で、とは言わねえけどよ?」
「──わかっている!」
恩着せがましい囁きから、ジャイルズは苦々しい舌打ちで目をそらした。「……何が望みだ」
「あんたの評判は聞いてるぜ。いやなに。ちょっと俺に、力を貸してくれりゃあ、いいんだよ」
この男は、手下が化け物に襲われているさなか、阿鼻叫喚の修羅場から、辛くもジャイルズを引っぱり出した。それで命からがら助かったのだ。あの場でぐずぐずしていれば、確実に死んでいただろう。それほど、化け物の動きは速かった。
だが、男の意図が分からない。
男が化け物の仲間であることは、特殊な風体が物語っている。あれは、男が遊民だからこそ、成し得た機転だったのだ。
男のにやけた笑いが不気味だった。
機転の利く回転の速さ、この肝のすわり具合、命を捨ててかかっているような、どこかが壊れているような危うささえある。
はたして思惑はどこにあるのか。
敵を助けた目的は? そうだ。なぜ、仲間を官憲に売り、組織を裏切るような真似をするのか。
裏切り者は「カルロ」と名乗った。
SIDE STORY 19 「調達屋の矜持」
( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
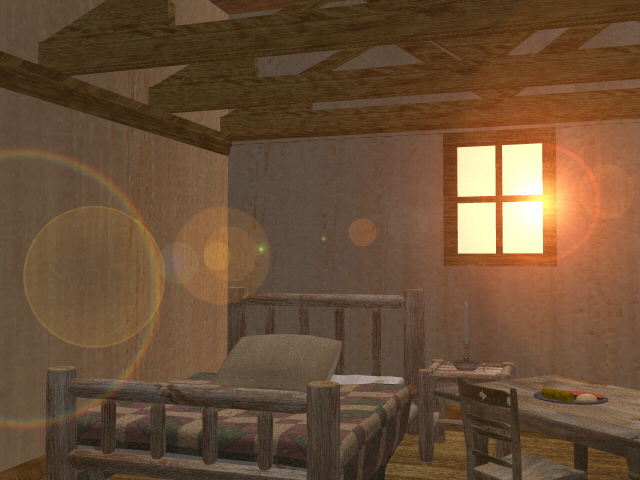
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》